経営者向け情報【1月12日更新】
今月号の目次
“家電量販店”モデルの先駆者!ピンチをチャンスに変え、新業態を開発したヤマダ電機・山田昇氏

家電の主な購入方法がメーカー系列店による訪問販売だった時代に、様々なメーカーの商品を店舗に陳列するという常識破りの販売方法を実践した株式会社ヤマダ電機。今回は、同社を創業した山田昇氏が、「家電量販店」という新業態を開発した際のエピソードを紹介したい。
カラーテレビの無料調整サービスで商機をつかむ
ヤマダ電機の前身は、日本ビクター(現JVCケンウッド)で活躍していた山田氏が、1973年に群馬県前橋にて立ち上げたヤマダ電化センターだ。松下電器産業株式会社(現パナソニック)の系列店、いわゆる「ナショナルショップ」としての創業であった。
家電製品は店頭ではなく各家庭への訪問販売で売られるのが主流だった1970年代、山田氏が売りとしたのがカラーテレビの無料調整サービスだ。当時一般的だったブラウン管テレビには、消耗品である真空管が使われており、良質な映像を保つには必ず部品交換などの調整が必要であった。山田氏は、これを無償で行うことによって人気を博したのである。
こうして家庭を訪問した山田氏は、カラーテレビを調整しつつ、その家で使われている家電製品を観察した。これらが全て松下電器製のものであれば、既に懇意にしている系列店があると考えられるため、割り込むのは難しい。一方、日立や東芝など、様々なメーカーの製品が置いてある家庭ならば、山田氏が松下電器の製品を売り込むチャンスがあった。
また、家の中に入ることで、その家庭の暮らし向き、家族構成、収入などに見当を付けることができた山田氏。それらの情報を顧客台帳に記録すると、家電製品を購入してもらえる可能性の高い顧客から順番に開拓していった。
創業から5年も経つ頃には、山田氏は自社を、5店舗を展開する年商9億円(現在の貨幣価値に換算)の優良企業へと成長させていた。社名はヤマダ電機に改称。同氏の経営者人生は前途洋々かと思われた。
危機突破から生まれた「量販店」
しかし、1980年代に入ると、新たな問題が山田氏の前に立ちはだかった。信頼して支店を任せていた優秀な社員が相次いで独立し、自身の店を構え始めたのである。
訪問販売での業績は、社員の営業スキルによって決まる。ヤマダ電機では、有能な人材が同社の優良顧客を引き連れて流出したことで売上が激減。対策を講じようにも、本店の経営で手一杯の山田氏には、支店を回って従業員教育を施している余裕はなかった。
「こうなっては、一旦支店を閉めて、経営資源を本店に集中させるしかない……」
増やしてきた店舗の閉店という苦渋の決断をした山田氏。これで経費削減にはつながったものの、今度は支店の抱えていた在庫が本店に移され、山のように積み上がった。
「1件ずつ訪問販売をしていては、いくら時間があっても到底売り切ることなどできない。それならば、顧客に本店まで来てもらおう」
そう考えた山田氏は、全商品を2割引とする旨を書いたチラシを作り、得意先の家庭に配布していった。すると、この「在庫一斉処分セール」に顧客が押し寄せ、在庫品はあっという間に売り切れたのである。
山田氏は後に、このときの衝撃を次のように回想している。
「私はそれまで、家電は訪問販売でしか売れないと考えていました。全商品を2割引にして店舗で売ったのはあくまで苦肉の策で、上手くいくかは未知数でした。東京や大阪といった、人口の多い大都市ならばいざ知らず、地方では店舗で家電を売るなど採算が合わないと思い込んでいたのです。しかし、それは大きな間違いでした」
この「在庫一斉処分セール」の大成功によって、山田氏は「家電量販店」モデルの将来性に気付いたのである。
顧客満足のためにはメーカーとの対立も辞さず
店舗での安売りを始めた山田氏に対して黙っていなかったのが、松下電器の指示通りに定価販売を行っている他の系列店であった。ヤマダ電機に顧客を奪われた彼らは、松下電器に状況を陳情。その結果、松下電器からヤマダ電機に対して、「売れ筋の商品を卸さない」「商品の供給量を減らす」といった“圧力”がかかった。
商品の仕入れができなければ、商売が成り立たない。だが、山田氏がこれに屈することはなかった。松下電器以外のメーカーや問屋など、正規以外のルートから商品を仕入れ、販売を続けたのである。
独自に仕入先を開拓して商品を揃えることは、松下電器の系列から離れることを意味した。また、こうした「メーカーに弓を引く」行為は、松下電器以外のメーカーからも非難を浴びる可能性をはらんでいた。
そうしたリスクを背負ってでも、山田氏が松下電器の系列店から離脱し、量販店への道を突き進んだのは、同氏が「従来の家電の販売方法は、顧客のことが考えられていない」と感じていたためである。
「家電の訪問販売は、メーカー本位の売り方です。系列店は自社の商品しか売らない以上、顧客には選択の余地がありません。各メーカーの商品を全て見せ、比較して好きなものを選んでもらう店を作った方が、よほど顧客のためになると思いました」(山田氏)
そして、この山田氏の考えは正しかった。「家電量販店」という新業態は、顧客から支持され、ヤマダ電機は毎年売上の記録を更新。最終的にはメーカーから「うちの商品を扱ってほしい」と売り込みが来るまでになった。
1992年に大型店舗の出店規制が撤廃されたことを追い風に、ヤマダ電機は全国のロードサイドに大規模な店舗を次々と出店。驚異的な成長を遂げ、2005年には家電量販店で初となる売上1兆円を達成した。
現在、家電業界では、ECの台頭によって従来の売り方に変革が求められている。そうした中でヤマダ電機は、家電だけでなく、住空間全体を提案する業態への転換を模索中だ。インテリア、住宅、リフォームといった事業に進出するなど、成長分野の開拓を試みている山田氏の、さらなる挑戦に注目したい。
四半世紀に渡り水産業界で活躍してきた元執行役員。社長のブレーンとして、2年で経常利益を倍増させる

株式会社旭魚市場(仮名)は、新潟県に本社を構える魚市場の運営企業である。長年築き上げてきた取引先との信頼関係によって、売上こそ保っていたが、社長の神原史彦(仮名)は同社の将来に危機感を抱いていた。
「このまま従来と変わらない仕事を続けていては、いずれ業績が後退していくだろう。新たな顧客との取引開始など、これまでとは異なる取り組みを行う必要がある」
しかし、新規営業の経験を持つのは社長の神原ただ一人。また、社員の平均年齢は高く、新たな取り組みに対して反発が起きることも予想された。
クライアント情報
- 事業概要
- 魚市場の運営
- 売上高
- 20億円~
- 経常利益
- 3000万円~
- 上場市場
- 未上場
- 設立年
- 1950年代
- 従業員数
- 30名~
そんな中でも、自身の右腕となるような幹部候補の人材を育成しようと試みてきた神原だったが、期待の若手社員は、芽が出ないうちに退職してしまう。そのたびに神原は「今まで育ててきた時間は一体何だったのだろう」と喪失感に駆られるのだった。
「これ以上、幹部候補の教育に時間と労力をかけられない。なんとか即戦力の人材を採用できないものか……」
このように悩む神原に対してレイノスが紹介したのが、生島清治(仮名)であった。
候補者 生島氏(仮名)について
- 年齢
- 40代(当時)
- 年収
- 1200万円(当時)
- 住所
- 宮城県仙台市
- 前職
- 水産物卸 執行役員
生島は、新卒で宮城県仙台市の水産物卸売を手がける企業に入社。鮭や鱒を中心に扱ってきた。国内のみならず海外の産地にも赴き、生産者からの加工原料の直接買い付けや、スーパーマーケットへの提案営業をした経験もある。
また、新規事業にも携わり、コンビニエンスストアや海外スーパーへの販路開拓、ECサイトの立ち上げまで手がけたこともあった。同社に25年間勤め、最終的には執行役員にまで昇進。経験の幅や残してきた実績は申し分なく、まさに神原の求めていた人材だった。
「生島さんは業界に精通しており、少し話をしただけで弊社の課題を見抜きました。この人ならば必ずや活躍し、私の右腕として旭魚市場を牽引してくれると感じました」と語る神原。「私たちがモデルケースとなって、“斜陽”と言われる魚市場業界の未来を照らしたい!同じ水産業に携わってきた者として、どうか力を貸してください!」と説いた。
この想いに心を打たれた生島。「経営が苦しくなり、トップが業績の拡大を諦めてしまっている市場も多いなか、神原社長は未来を見据えて行動しようとしている。この人となら、やりがいのある仕事ができる!」と考え、移籍を決意した。
業績を数値で可視化。課題を的確に把握する
こうして旭魚市場に入社した生島は、県内のスーパーや魚屋を訪問して関係を築くとともに、社員の意識改革につながる仕組みの構築に着手した。
例えば同社では、社員が業績の数字を正しく把握できていなかった。社員の過半数は30年、40年と長期間在籍してきたベテランで、担当する業務の成果を感覚のみで大雑把に捉える習慣が染み付いていたのである。
この問題を認識した生島は、売上や利益を可視化するため、定期的に会議の場を設け、数値を用いて業績を報告させた。これにより、各部門は週1回、全社でも月1回は実績を共有。「スーパーへの販売を手がける部門の売上が、前年同月比1.7%減った」という具合に問題点が分かるため、それに対する解決策を議論することが可能となった。
SNSへの投稿から新規契約も
旭魚市場の将来を支える若手の採用活動についても、生島は改革を進めた。
具体的には、自社のホームページを刷新。これまでは文章による説明ばかりであったが、現場の写真を散りばめ、視認性の高いデザインにするなど、工夫を凝らした。
また、インスタグラムをはじめとするSNSも始めた。堅苦しい内容ではなく、現場で活躍する社員の生の声を掲載することで、投稿を見た人に「やりがいがあり、楽しそうな会社だ」と感じてもらえるように意識している。
こうした取り組みの効用は、採用促進にとどまらない。SNSへの投稿がきっかけとなり、居酒屋との新規契約が決まるなど、営業手法の1つとしても役に立っているという。
「前職でECサイトの構築とウェブマーケティングに関わっていたので、その経験を活かせています」と語る生島。様々な方向から旭魚市場の改革を進めていく彼を、社長の神原も高く評価している。
「生島さんのおかげで、今までになかった変化が会社に生まれました。現在進行中のプロジェクトは、生島さんがいなければ、取り組もうとさえ思えなかったものばかり。彼は理想の右腕です」(神原)
これらの施策の結果、生島が入社して2年で、旭魚市場は売上が15億円から20億円、経常利益が1500万円から3000万円に伸長した。
全国に魚を届けられる企業に
「顧客が求めている魚の種類と量を常に把握し、それを配送できるだけの物流網を構築すれば、旭魚市場は新潟にとどまることなく、全国に魚を届けられる会社になると思っています」
今後の旭魚市場について、そう展望を語る生島。彼の掲げるビジョンには、社長の神原も大いに期待している。
「生島さんの参画によって、若い人材の採用活動や社内環境の改革など、5年先、10年先を見据えた組織づくりに取り組めています」
変化を恐れず、挑戦を続ける社長と、様々なプロジェクトを実現へと導く優秀な右腕。この二人三脚が続く限り、旭魚市場の未来は明るいものとなるだろう。
<終>
【スカウト候補者一覧】逆境を覆し成果を残し続ける猛者たち

『レイノス』がこれまでお会いしている候補者について、情報共有いたします。
もし、詳細をお聞きになりたい場合、右上の電話マーク、もしくはメールにてお問い合わせくださいませ。
■候補者 松江順平 氏(仮名)
- 所属企業
- インターネットサービス業
(売上高:1000億円~) - 部門
- WEBマーケティング部
- 役職
- 部長クラス
- 年齢
- 41歳
- 年収
- 1000万円
●2017年には年間で10億円の粗利を創出。全社員の中で最も高い業績を残した社員に与えられる年間MVP賞を受賞した。
●WEB広告を中心に、プロモーション戦略の立案から営業活動、戦術実行まで幅広い知見を有している。
●WEBサイトのディレクションからECの運用、リアルイベントの実行など関連分野において豊富な実績がある。
■候補者 鮫島晴之 氏(仮名)
- 所属企業
- ハウスメーカー
(売上高:3000億円~) - 部門
- リフォーム事業部
- 役職
- 課長クラス
- 年齢
- 37歳
- 年収
- 1200万円
●新規営業に従事しており、自身が管掌する課の営業利益率を3年で4ポイント(18%→22%)向上させた。
●戸建住宅の販売を担当していた頃は、約600名の営業担当者の中で上位10%の実績を残していた。
●同社で課長を務める社員は約60名いるが、30代以下の課長は4名しかいない。
■候補者 吉川俊介 氏(仮名)
- 所属企業
- 旅行代理店
(売上高:1000億円~) - 部門
- 営業部
- 役職
- 課長クラス
- 年齢
- 36歳
- 年収
- 800万円
●30歳のとき、歴代最年少で課長に昇進。
●2年前から首都圏の支店にて責任者を務めている。同氏が支店長に就任してから、受注率は1.5倍、売上は2.5倍に伸長した。
■候補者 大森千佳 氏(仮名)
- 所属企業
- 住設機器商社
(売上高:1000億円~) - 部門
- 法人営業部
- 役職
- 係長クラス
- 年齢
- 32歳
- 年収
- 800万円
●全国に600名以上いる営業担当者のなかで、常に上位5%以内の業績を残している。
●同期60名中、最速で係長へ昇進。現在15名の部下のマネジメントを手がけている。
●現在は、ハウスメーカー、設備工事会社、リフォーム会社などへの新規営業を担当している。
■候補者 坂上雄大 氏(仮名)
- 所属企業
- 精密機器メーカー
(売上高:1000億円~) - 部門
- 営業部
- 役職
- 主任クラス
- 年齢
- 29歳
- 年収
- 600万円
●入社5年目に、全国の営業担当者150名中1位の成績を残した(年間粗利2.5億円)。
●同期100名中、最速で主任に昇進。
●現在は、メンバー6名を管掌し、プレイングマネージャーとして従事している。
■候補者 安田健次郎 氏(仮名)
- 所属企業
- 総合スーパー
(売上高:1000億円~) - 部門
- 店舗運営部
- 役職
- 店長
- 年齢
- 34歳
- 年収
- 600万円
●アルバイトを含む約50名のスタッフを管掌している。昨年度の離職率は全60店舗中最も低く、売上は前期比15%増となる20億円だった。
●60名の店長のうち、最も評価が高い社員が選ばれる社長賞を受賞した経験がある。
■候補者 岡隆太 氏(仮名)
- 所属企業
- 物流業
(売上高:100億円~) - 部門
- エリア統括
- 役職
- 課長クラス
- 年齢
- 42歳
- 年収
- 900万円
●配車管理や運行管理等に従事し、36歳のとき歴代最年少で課長に昇進。
●採用活動や従業員教育にも携わり、リーダーやマネージャーの育成に注力する事で自身が管掌するエリアの役職者比率を8ポイント引き上げた。
●現在はエリア統括として7ヶ所の営業所を管掌しており、同氏の担当エリアの売上は1年で30億円から33億円へと拡大した。
■候補者 真田俊也 氏(仮名)
- 所属企業
- 物流業
(売上高:5000億円~) - 部門
- 物流センター
- 役職
- センター長
- 年齢
- 39歳
- 年収
- 1000万円
●主に宅配の荷物を手がけており、ドライバーに対する教育・研修などを実施。クレーム案件の共有などを定期的に実施し、年間のクレーム発生件数を20%引き下げた。
●同期200名中、最速で課長に昇進。
●現在は物流センターの管理及び営業活動に従事しており、昨年度は年間で売上65億円、粗利10億円の業績を残した。
■候補者 湯川真紀子 氏(仮名)
- 所属企業
- 施設内装の企画制作会社
(売上高:1000億円~) - 部門
- 法人営業部
- 役職
- 課長クラス
- 年齢
- 37歳
- 年収
- 900万円
●入社以来、一貫して企画提案型の営業に携わってきた。最近では、JR東日本などの大手顧客を担当し、自身の課の年間予算は約40億円に上る。
●昇進・昇給スピードは、同期約30名中1位。現在、同社の最年少課長である。
■候補者 金山雅治 氏(仮名)
- 所属企業
- トヨタ系自動車ディーラー
(売上高:1000億円~) - 部門
- 営業部
- 役職
- 主任クラス
- 年齢
- 34歳
- 年収
- 1100万円
●トヨタ車の新車販売に従事し、毎月約13台を販売している(同社の営業担当者の平均販売台数は月6~7台)。
●営業順位は、全営業担当者900名中、18位(2016年)、22位(2017年)、9位(2018年)。
●2019年からはマネージャーとして、店舗運営も担っている。
■候補者 高義信 氏(仮名)
- 所属企業
- 外食チェーン
(売上高:500億円~) - 部門
- 海外営業本部
- 役職
- 課長クラス
- 年齢
- 37歳
- 年収
- 800万円
●M&Aの候補企業への買収監査を行い、ロサンゼルスのレストラン2社の買収及びPMIにおいて実務を担当。
●海外子会社3社の目標に対する予実管理、及び資金調達計画の策定を手がけた。
●創業100年になる老舗ブランドの海外進出を支援した。
■候補者 中山三郎 氏(仮名)
- 所属企業
- ハウスメーカー
(売上高:1兆円~) - 部門
- 工事部
- 役職
- 課長クラス
- 年齢
- 40歳
- 年収
- 1300万円
●鉄筋コンクリート造、同社オリジナルパネル工法による新築マンションの施工管理業務に従事。
●昇進・昇給スピードは同期70名中トップクラス。
●31歳のとき、複数のエリアを管掌する統括所長職に同社最年少で抜擢された。
■候補者 小林隆 氏(仮名)
- 所属企業
- 自動車部品メーカー
(売上高:300億円~) - 部門
- 品質管理部
- 役職
- 役員クラス
- 年齢
- 58歳
- 年収
- 2000万円
●トヨタ自動車を主要取引先とする部品メーカーにて、設計・営業の経験を経て品質保証部長を務めた後、取締役常務に就任。
●トヨタ自動車より品質管理優秀賞を受賞したことがある。
■候補者 大竹哲也 氏(仮名)
- 所属企業
- 精密機器メーカー
(売上高:300億円~) - 部門
- 海外事業部
- 役職
- 事業部長クラス
- 年齢
- 57歳
- 年収
- 1200万円
●工場にて、作業員1人あたりの労働生産性を2ヶ月で3倍にし、工場の人員規模を2年で10倍に成長させた。
●赤字を発生させていた事業部にて、市場分析、販売戦略の見直し、徹底したコスト管理などにより大幅な黒字化を実現。損益分岐点比率50%の収益体質を構築し、リーマンショックにおいても黒字を維持した。
●売上高1兆円を超えるグループ全体の構造改革で、中心的な役割を果たした。
■候補者 戸田健一 氏(仮名)
- 所属企業
- 金型メーカー
(売上高:100億円~) - 部門
- 技術部
- 役職
- 課長クラス
- 年齢
- 40歳
- 年収
- 800万円
●食品や薬品の容器用キャップや医療機器の部品に用いられる金型の設計に従事しており、CADシステムを自作した。CADシステムへの機能の追加を外注する場合、1種類につき15~20万円の開発コストがかかるものだが、同氏は自身の手で80種類も機能を追加した。
●キャップの金型製造は難易度が高く競合が少ないため、1件あたりの利益は3000万円に上る。同氏は9名の部下を管掌し、そういった金型を1人あたり月間3件も設計させている。
●射出技能検定において特級の資格を有しており、試作品の製作も可能。
コロナ禍における顧客開拓に新手法!“ウェビナー”を視聴した見込み顧客の氏名や連絡先を獲得できるサービスとは
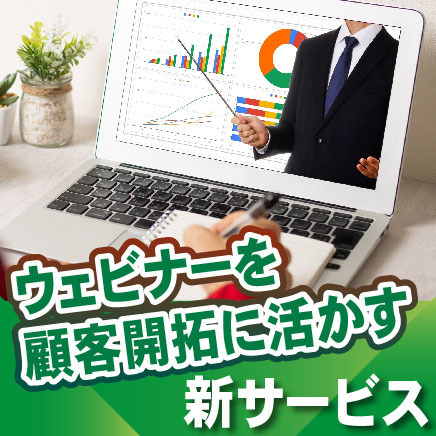
コロナ禍で対面営業が制限されるなか、“ウェビナー”の動画を使った営業支援サービスが広がりつつある。ウェビナーとはウェブとセミナーを合わせた造語で、企業がセミナーなどをウェブ上で配信することを指す。
企業が参加者を会場に集める必要がないため、“密”を回避しつつ講演を開く手段として昨今注目されている。
ただ、通常のウェビナーには、参加者がアンケートなどで情報を提供しない限り、主催する企業が参加者の連絡先を集められないという問題がある。せっかく企業が開催しても、参加した見込み顧客に後日接触することが難しいのだ。
そこで、企業が会員制サイトにウェビナーの動画を公開し、その動画を再生した会員の氏名や連絡先を収集できるという新たなサービスが生まれている。
ウェビナー参加者の情報を確実に入手できる仕組みを構築することで、企業はオンライン上での営業活動を実施しやすくなる。
過去に使用したウェビナーの動画を活用できる「ウェビナールーム」
企業から商品やサービスを紹介する動画を集め、ポータルサイト上で無料公開する新サービスが「ウェビナールーム」だ。「現状のウェビナーは単発で終わってしまい、継続的に見込み顧客を獲得することが難しい」という課題の解決を目指している。
企業側が過去のウェビナーで使用した動画と説明資料を提供すれば、同サービスを運営する株式会社ヒトクセが1~2週間でウェビナーを掲載する特設ページを作成する。ひとたびページを用意すればウェブ上で繰り返し使えるため、営業効率がいい。
サイトの利用者は会員登録をすることにより、こうしたウェビナー動画を無料で視聴できるようになる。ただし視聴の際は、氏名や職業、視聴した動画といった情報が企業側へ提供されることに対し、あらかじめ同意しなければならない。株式会社ヒトクセは会員の利用データを1件2000円前後で企業に販売しており、企業側はこれを次の営業活動に生かすというビジネスモデルだ。
今年1月のリリース予定で、すでにマーケティングや広告、コンサルティングなどを手がける約50社が動画を提供しているという。
動画の企画段階から支援を受けることができる「セミナーシェルフ」
ウェビナー動画の撮影から編集、サイト掲載と見込み顧客の情報提供までを一貫して請け負うのは「セミナーシェルフ」というサービスだ。
法人営業支援を手がける株式会社イノベーション(東証マザーズ上場)によって運営されており、初期費用は制作料を含めて10万円。動画を視聴した見込み顧客の情報を、本人の同意を得て1件ごとに有料で企業へ提供している。
同サービスは、2020年4~6月期の会員数が1~3月期より50%増え、7~9月期は4~6月期からさらに30%増えた。企業からの問い合わせ数も、コロナ禍前の2月に比べて3倍以上になっているという。
自社サイトでの“新規営業”は成功しにくい
コロナ禍の収束が見通せないなか、不特定多数の来訪者を集める展示会やイベントの開催は難しい状況が続いている。
そこで、オンライン上での営業活動に注目が集まっているのだが、自社のウェブサイトに商品紹介を並べただけでは集客力に欠ける。自社サイトを訪れるのは既存顧客に偏りがちなため、新規顧客の獲得にもつながりにくい。
そういった課題を解決する手段として、ウェビナー動画の制作支援や集客代行のサービスに企業の関心が集まっているのだ。
ウェビナーやテレワークに使用するウェブ会議サービスの市場は今後も拡大が続く見込みだ。調査会社の株式会社アイ・ティ・アールによると、国内における2019年度の市場規模は、前年度の20%増となる111億円だった。コロナ禍を受けて市場はさらに広がり、2020年度は197億円、2024年度には364億円になると予測されている。
ウェビナーを通じて自社の商品やサービスの特徴を知ってもらい、それを突破口に電話やメールなどで商談を行う。そうした“動画営業”が定着すれば、営業担当者の業務効率を向上させることにつながるだろう。
訪問営業に代わる新たな営業手法として、導入を検討してみてはいかがだろうか。
“売って終わり”の製造業から脱却!ヤマハ発動機、製品から収集したデータを駆使して新サービス提供につなげる

ヤマハ発動機株式会社が、インターネットに常時接続する“つながるバイク”を販売し始めた。アプリを通じ、ユーザーに燃費データや故障情報などを提供。顧客の用途に応じた性能変更や、旅行の提案といったサービスも視野に入れる。
「モノを売って終わり」ではなく、自社に蓄積されたデータを駆使して新たなサービスを開発し、顧客との接点を増やす考えだ。
インターネットに接続する車は「コネクテッドカー」と呼ばれ、米テスラの製品を筆頭に四輪車では既に存在するが、二輪車としては先進的だ。二輪車には通常、カーナビのような画面がなく、道案内などのために運転手が情報を得る手段が限られる。アプリで目的地情報などがわかる意義は大きい。
また、二輪車はツーリングなどの趣味のために購入するユーザーが多い。旅を支援したり、仲間同士によるコミュニケーションを促したりする機能との親和性は高いとみられる。
バイクが自ら燃費データや故障情報を提供
ヤマハ発動機は昨年2月より、同社にとって最大の二輪市場であるインドネシアにて “つながるバイク”の販売を開始した。
スマートフォンのアプリが無線通信「ブルートゥース」を介し、バイクの制御装置に集まるエンジンの回転数や走行距離、車両位置などの情報を取得。利用者はアプリで燃費を確認したり、故障の警告を受信したりできる。
二輪車大国のインドネシアでは、車両が街中にあふれているが、愛車の位置がスマホに表示されるため、混雑した駐車場でも見つけやすくなる。
ヤマハ発動機は蓄積したデータを、故障の原因分析や商品企画などにも生かす。また、車両のソフトを更新する機能の提供も目指している。
執行役員兼IT本部長を務める山田典男氏は「モノを作って売るだけではなく、顧客に応じた体験やサービスを提供し、収益を得る機会を広げたい」と語る。
サービスの例になりそうなのが、欧米で手がける「デスティネーション」と呼ぶプログラムだ。同社が世界各国にある絶景ツーリングスポットなどを紹介するもので、将来は顧客ごとに旅行を提案するサービスも思い描く。
このように、ヤマハ発動機は“つながるバイク”を駆使して顧客との接点を広げようとしている。まずは今年中に全世界における販売台数の4%にあたる20万台以上を供給。2030年までに全製品にネット接続機能を盛り込む。
目指すは、今後10年間での2億台販売。主力の二輪の販売台数は足元で年間500万台のため、かなり野心的な目標だ。
インド全土を網羅する300店舗でオンライン販売に対応
そんなヤマハ発動機を含め、二輪業界共通の課題となっているのが、デジタル技術に幼少期から親しんだ若い層の開拓だ。こうした層はバイク店を縁遠く感じ、購入にも消極的という状態が続いてきた。
そこで同社は、オンライン販売によって顧客と接点を持つ取り組みも始めた。例えばインドのECサイトでは、製品を選ぶと画像が拡大され、あらゆる角度から確認できるようになっている。購入品の受け取りやメンテナンスのために来店する必要はあるが、オンラインで申込金を支払い、購入予約まで行うことが可能だ。
インドでは、昨年10月中旬までに全国をカバーする実店舗300店にて、オンラインで購入した商品を受け取れるようにした。残り200店にも順次対応する。ブラジルでも、今年から本格的にECサイトを展開予定。他の地域にも採り入れていくという。
ヤマハ発動機の改革の背景にあるのは危機感だ。同社の調べによると2019年の二輪車の世界市場は5336万台。東南アジアやインドなど新興国がけん引し、10年前から8%拡大したものの、ヤマハ発動機の販売台数は505万台と同期間で13%減り、世界シェアも9.5%と2.3ポイント低下した。
東南アジアでは、世界首位のホンダ(世界シェア36.6%)から攻勢をかけられている。世界最大の市場インドでは、世界2位で現地資本のヒーロー・モトコープ(同12.8%)などが強い。
競合企業に先駆けた“つながるバイク”で、どこまで巻き返せるか。ヤマハ発動機の取り組みは、製造業が「モノを売って終わり」のビジネスから脱却できるかを見定める試金石となりそうだ。
“空飛ぶクルマ”市場への新規参入が活発に。中小企業やスポーツ用品メーカーも!

空間を垂直離着陸で移動する“空飛ぶクルマ”の実用化を見据え、様々な企業による関連市場への参入が相次いでいる。
新規参入しているのは、自動車や航空機関連の大手部品メーカーばかりではない。
従業員約50名の中小企業やスポーツ用品メーカーのなかにも、自社の強みを生かして部品を開発している企業がある。企業規模や業種に関わらず、技術力次第で取引先を開拓できる可能性を秘めている。
“空飛ぶクルマ”に関連する世界市場は160兆円に膨らむとの試算もあり、各企業はセンサー類や外装などの製造に商機を見いだす。
“空飛ぶクルマ”開発コンテストでの快挙を支えた中小企業
2020年2月末、1人乗りの小型航空機を開発するコンテスト「GoFly」の最終審査が行われた。メインスポンサーは米ボーイング。世界の800超のチームが書類審査などで2年かけて絞り込まれ、最後の飛行テストには24チームが進んだ。
その中で、日本から参加した新興企業のテトラ・アビエーション株式会社は革新的な機体に与えられる「ディスラプター賞」を受賞した。
同社を支えたのが、埼玉県で複合材料の加工を手がけているUCHIDAだ。
空飛ぶクルマは滑走路が不要のため、大規模なインフラを整備しなくても交通の利便性を高められると期待されている。機体を自在に動かして垂直離着陸するためには、推力と機体の軽量化が欠かせない。
そこで白羽の矢が立ったのが、軽量で高強度な炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の成型加工を得意としている株式会社UCHIDAだった。同社はコンテストの1年ほど前の、製品を構想する段階からテトラ・アビエーションに協力。機体における外装部品の大半と、プロペラの周りに円形の囲みをつけて推力を高める「ダクテッドファン」を提供した。
UCHIDAは従業員約50名の中小企業ながら、重工メーカー向けに航空機部品などの試作開発を行ってきた実績を持つ。1点1点が異なる試作部品を職人技で仕上げたり、開発初期から顧客に深く関わり、コストを抑えた設計を助言したりできるのが強みだ。
2011年にはイタリア企業が空飛ぶクルマを試作した際に協力したこともあり、その経験にテトラ・アビエーションが目を付けた。
ダクテッドファンではUCHIDAの技術力が生きた。プロペラは高速で回転するが、囲いとの間が空きすぎてしまうと推力が生まれない。そのため同社は、CFRPの高い加工技術を発揮して、プロペラの周りにわずかな隙間しかできないように設計した。
「UCHIDAの担当者は『緻密にCFRPを加工し、誤差を1ミリ以内に抑えた』と語る」
参考元:(空飛ぶクルマ) 航空・車部品、強み生かし参入|日本経済新聞
CFRPは航空機や自動車部品などで使われており、小さな動力で機体を浮かせる必要のある空飛ぶクルマには欠かせない素材になると見られている。UCHIDAはテトラ・アビエーションへの部品提供で加工技術をアピールし、試作などの受注拡大につなげたい考えだ。
スポーツ用品メーカーも参入。独自技術を座席の開発に転用
スポーツ用品大手のミズノ株式会社も、国内で空飛ぶクルマの実用化を目指している株式会社スカイドライブなどと乗員用シートの性能確認試験を始めた。
2023年に機体の実用化を目指しており、ミズノはそれまでに大手自動車部品メーカーなどと共同でシートの開発を進める。
ミズノは座席の下の衝撃緩衝装置にランニングシューズのソール構造を応用。同社のランニングシューズは、樹脂製の波形プレートを2枚重ねることで、衝撃を吸収するクッション性と安定感を両立している。空飛ぶクルマの座席では強度と加工のしやすさから樹脂をアルミニウム合金に変更。衝撃を吸収する部分の形も、連続する波ではなくひし形を波状に組み合わせたものに変えた。
この衝撃緩衝装置は構造がシンプルで軽量化しやすいほか、既存の技術を応用することで、素材や形状を一から考えるよりも短い期間で開発できた。
2020年3月の試験では、一般的な航空機の座席に比べ乗員の腰椎への負担を減らせる可能性があることがわかったという。スカイドライブが現在開発している機体にはまだ活用されていないが、2023年までに実際に使えるよう開発を進める。
複数の製品の販路開拓を進める電子部品メーカー
電子部品メーカーの中でも空飛ぶクルマに注力し、積極的に展示会へ出展しているのがタイコエレクトロニクスジャパン合同会社(以下、TEジャパン)だ。
同社は自動車や電子機器の配線用コネクターなどで高いシェアを誇る。空飛ぶクルマを電気自動車やファクトリーオートメーションと並ぶ成長市場の1つと位置づけ、早くも顧客開拓に動いている。
TEジャパンが空飛ぶクルマ向けに供給する部品の1つが、機体の傾きを検知するために使う位置センサーだ。
空飛ぶクルマは航空機やヘリコプターに比べて小型で、推力に限界がある。全重量に対して乗員の体重が占める割合が大きいため、不安定になりがちだ。緻密に機体を制御するには、機体の傾きを把握する技術がカギを握る。
同社は高度を測る気圧センサーや温度センサーなどもラインアップにそろえる。そのほかにも、バッテリーから流れる電流を必要な場所に送るために電圧を制御する「スイッチングリレー」や、軽量の配線ケーブルの採用も狙う。
実際、傾きを測るセンサーやスイッチングリレーについては、空飛ぶクルマの国内スタートアップがすでに性能評価を進めているという。
TEジャパンはITや家電の見本市、「CEATEC(シーテック)」で2019年から2年続けて空飛ぶクルマをテーマに出展。スイスに本社を置くTEコネクティビティーのグループ全体でも、空飛ぶクルマを通してモビリティー事業を拡大しようとしている。
「空飛ぶクルマ」関連の巨大な市場では、中小企業や異業種の企業を含む様々なメーカーが販路開拓や製品の開発を進めている。親和性の高い製品を手がける企業は、参入を検討してみてはいかがだろうか。
【紹介可能な顧問一覧】コロナ禍を乗り切るうえでの強力なパートナーたち
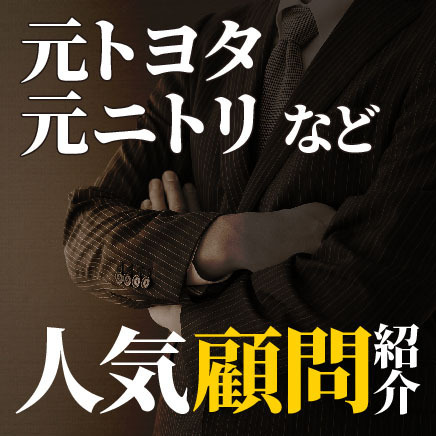
※すぐにご紹介いたします。詳細をお聞きになりたい場合、右上の問い合わせボタンよりご連絡ください。(電話、メール、いずれも対応可能です)
■顧問 山路剛 氏(仮名)
- 出身企業
- 富士通株式会社
- 最終役職
- 執行役員クラス
- 年齢
- 65~70歳
- 支援内容
- 人脈を活用した新規販路の開拓、営業部門の強化、クラウド・AI・IoT化の促進
■顧問 小木正文 氏(仮名)
- 出身企業
- 株式会社ニトリホールディングス
- 最終役職
- 執行役員クラス
- 年齢
- 65~70歳
- 支援内容
- ニトリグループへの販路開拓、店舗戦略の立案、小売業の業務効率化、マニュアル整備
■顧問 藤沢雄一 氏(仮名)
- 出身企業
- 株式会社東芝
- 最終役職
- 取締役クラス
- 年齢
- 60~65歳
- 支援内容
- 幅広い業界に対するトップ人脈の活用、グローバル人材の採用・育成
■顧問 松井平太 氏(仮名)
- 出身企業
- 積水ハウス株式会社
- 最終役職
- 取締役クラス
- 年齢
- 75~80歳
- 支援内容
- 積水ハウスへの販路開拓、ハウスメーカーの収益体質改善
■顧問 田辺忠彦 氏(仮名)
- 出身企業
- スギホールディングス株式会社
- 最終役職
- 執行役員クラス
- 年齢
- 65~70歳
- 支援内容
- 経営指導、社外取締役、非常勤監査役
■顧問 甲斐晴基 氏(仮名)
- 出身企業
- トヨタ自動車株式会社
- 最終役職
- 理事クラス
- 年齢
- 70~80歳
- 支援内容
- 工場の生産性改善、海外工場指導
■顧問 早瀬耕史 氏(仮名)
- 出身企業
- 丸紅株式会社
- 最終役職
- 取締役クラス
- 年齢
- 60~70歳
- 支援内容
- 営業力の強化、中国・台湾への進出、人脈を活用した販路開拓
■顧問 大久保廉太郎 氏(仮名)
- 出身企業
- アサヒビール株式会社
- 最終役職
- 取締役クラス
- 年齢
- 60~70歳
- 支援内容
- アサヒグループへの販路開拓、飲料業界における生産・購買・物流部門の改善
■顧問 穂積利光 氏(仮名)
- 出身企業
- 住友商事株式会社
- 最終役職
- 執行役員クラス
- 年齢
- 70~75歳
- 支援内容
- 海外進出におけるアドバイス
■顧問 河内さつき 氏(仮名)
- 出身企業
- NTTドコモ/ドコモグループ子会社
- 最終役職
- 取締役クラス
- 年齢
- 60~70歳
- 支援内容
- 非常勤監査役、リスクマネジメント強化