経営者向け情報【2月9日更新】
今月号の目次
訪問営業を封じられた年商40億円の物流企業、オンラインセミナーを活用し新規開拓を目指す!

コロナ禍によって顧客への訪問営業が行いにくくなるなか、“ウェビナー”を活用した営業手法に注目が集まっています。
“ウェビナー”とは、“ウェブ”と“セミナー”を合わせた造語で、企業がオンライン上で配信するセミナーのことを指します。
参加者を会場に集める必要がないため、 “密”を回避しつつ見込み顧客の情報を獲得できる取り組みとして開催されるようになりました。
しかし、従来のウェビナーには「担当者がデジタルツールに不慣れで準備が滞る」「来場者の情報を正確に記録できない」「アンケートに回答してくれた来場者の連絡先しか分からないので、見込み顧客のリストが増えにくい」などの課題があり、売上につながらないという事態が発生していました。
そこで、最近ではウェビナーの開催からその後の営業活動まで支援するサービスが生まれています。
ウェビナーの準備から開催後の営業活動までサポートする新サービス
オンライン名刺管理サービスを手がけるSansan株式会社によって2020年10月から提供されている「Sansan Seminar Manager」は、ウェビナーの運営を包括的にサポートするサービスです。
参加者募集ページの作成から、開催情報の送付、受付での連絡先の収集、アンケートの集計まで、様々な機能を網羅。同サービスを利用すると、専門的な知識がなくとも最短10分で参加者募集ページを作成できるようになります。
また、これまではウェビナー視聴用のURL発行、メール送信、受付、来場者の情報管理といった業務には異なるツールを使う必要がありました。「Sansan Seminar Manager」ではそれらを同じツール上で完結できるため、ウェビナー運営にかかるコストの大幅な削減にも役立ちます。
ウェビナー導入で販路拡大を目指す物流会社、1人の若手社員にプロジェクトを一任
同サービスの導入を契機に、営業のデジタル改革を進めているのが、売上40億円の株式会社トヨコンです。
倉庫管理、顧客の商材に適した包装材の設計、在庫管理などを請け負う総合物流会社の同社。約40人の営業担当者は訪問営業を中心に行っていましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大以降は営業が全くできない状況が続いたそうです。
そこで、デジタルマーケティング推進担当の浦部将典氏はウェビナーに活路を見出しました。
ウェビナーに取り組む上で障壁となったのは、コンテンツ制作よりも、運営に関わる裏方作業。浦部氏は、「社員はウェビナーの企画や台本制作に時間を割くべきだ」と判断し、「Sansan Seminar Manager」を導入しました。
浦部氏はこのツールを活用したイベント運営を、他部門から異動してきた若手社員の細井あゆみ氏に一任しました。細井氏はデジタルに長けた人材というわけではありませんでしたが、「誰にでもセミナー運営ができると証明されれば、全社的な活用が可能であることの証左になる」と考えた浦部氏は、あえて任せることにしたのです。
初開催のウェビナーで、参加者の約半数の連絡先を獲得!
こうして、細井氏の指揮の下でウェビナーを開催することになったトヨコン。ウェビナーのテーマは「ロボットを活用した倉庫業務の省人化」で、対象として細井氏が選定した企業は約1200社でした。
参加希望者にはウェビナーの実施前に、セミナー管理ツールからリマインドメールを送りました。全くの素人だった同氏でも、滞りなく集客から実施まで進めることができたといいます。
ウェビナーを実施したのは20年11月。企画や台本制作は浦部氏が担い、営業の担当者が講演しました。参加者は35人で、そのうちアンケートに回答したのは約半数の16人でした。
アンケートを集計したところ、回答者のうち4人が、ウェビナーのテーマである「ロボットを活用した倉庫業務の省人化」に前向きであることが判明。まずはその4人に対して、営業担当者が商談を始めたそうです。
「月2回のペースでウェビナーを実施したい」と意欲を見せる浦部氏。「デジタルツールを活用して1つでも受注実績をつくり、営業部門の意識を変えなければならない」と変革を急いでいます。
このように、コロナ禍下でも成果を出そうとする企業は、ウェビナーの運営を支援するサービスを活用しています。
デジタル技術に対するリテラシーの低さからウェビナーを敬遠している企業も、新たな営業手法の一つとして導入を検討してはいかがでしょうか。
自動改札機、ATM、自動券売機……数々の“世界初”を生み出したオムロン創業者・立石一真氏
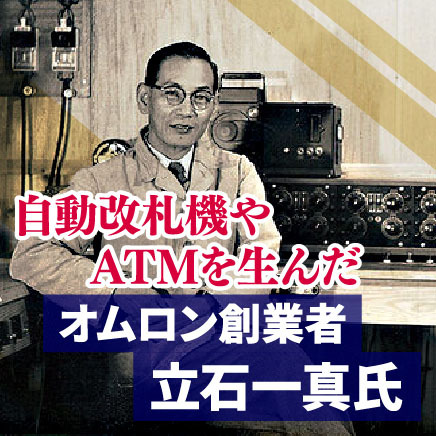
産業用の制御機器から個人向けの健康医療機器まで、幅広い分野で存在感を示す電気機器メーカー、オムロン。世界に先駆けてATMや自動改札機を開発するなど、様々な領域での「オートメーション(自動化)」を牽引してきた。今回は、そんな同社を一代で築き、最先端の技術力を誇る企業へと育て上げた立石一真氏を紹介したい。
オートメーションを事業の柱に据える
立石氏は1900年、熊本県にて生まれた。地元の工業学校を卒業した後、兵庫県庁、電機メーカーへの勤務を経て独立。1933年に、オムロンの前身である立石電機製作所を立ち上げた。
同社は、レントゲン写真撮影用のタイマーや、電気回路を制御する装置を開発。戦時中には東京大学航空研究所からの依頼を受け、航空機に使われる小型スイッチの製品化に国内で初めて成功するなど、技術力を高めていった。
終戦を迎えてからも、立石電機製作所は電気コンロやヘアアイロンといった電熱機器を手がけ、新商品の開発には余念がなかった。しかし、同社の稼ぎ頭は大手企業に納品している電気回路の制御装置であったこともあり、立石氏は危機感を募らせていた。
「これまで通り事業を続けていても、大手メーカーの下請け企業のままだ。今後、立石電機が飛躍していくためには、新しい領域を開拓せねばならない」
そうした中、とある講演にて、立石氏は「オートメーション」という言葉に出会った。そこでは、以下のような内容が語られていた。
「近年の米国では、オートメーション工場というものが生まれている。これは無人の工場のことで、機械に原料を入れると、自動的に製品ができあがるという代物だ。これからの製品は、こうしたオートメーション工場にて生産されることになるだろう」
次のマーケットを探り続けていた立石氏は、「オートメーションこそ、立石電機の未来を切り拓く分野になる!」と直感。すぐさま渡米すると、1ヶ月にわたってシカゴ、サンフランシスコ、デトロイトなど10都市のオートメーション工場を視察した。そして、日本にも自動化の波が訪れることを確信し、オートメーションに関わる機器の開発を決めたのである。
「ソーシャル・ニーズ」を捉え、商機をつかむ
立石氏は、「社会が必要としているもの」のことを「ソーシャル・ニーズ」と呼び、これを満たす技術や商品の開発を基本戦略としていた。オートメーション用の制御機器を開発するにあたっても、同氏は社員に対し、「取引先から多くのソーシャル・ニーズを聞き出してくるように」と指示した。
「我が社の社員の仕事は、今ある商品を売ることだけではない。次に売る商品を開発するためのニーズをつかむことも、彼らのもう一つの仕事だ。ソーシャル・ニーズに基づき、独自に開発した商品は、社会から必要とされているがゆえ、自然に売れるのである」(立石氏)
こうして社員が集めてきた「ソーシャル・ニーズ」の中でも特に多かったのが、「電気制御を行うスイッチの寿命を飛躍的に延ばせないか」という要望であった。
それまでのスイッチには、金属と金属を触れ合わせるための接点があり、何らかの力を加えてこれを接触させることで、電流が流れる仕組みとなっていた。接点は、電流が切れる際に生じる小さな火花によって徐々に摩耗していく。
もし機械が自動化されると、スイッチの接触回数はケタ違いに増えるため、現状の製品ではわずか1週間で使えなくなってしまうことが予測できた。そのたびに機械を止めてスイッチを交換するのでは、時間的なロスが大きすぎる。さりとて、自動化に耐えうるスイッチを作るとなると、その寿命を最低でも1000倍には引き上げねばならなかった。
世界初、“無接点スイッチ”を開発
当然、これまでと同じ構造では、寿命を1000倍に延ばすことなど不可能である。そこで立石氏は発想を転換させ、「スイッチの寿命が短いのは、そもそも接点があるからだ。これを無くしてしまえば、金属の摩耗自体が無くなり、寿命も延びるだろう」と考えた。
加えて同氏は、当時ソニーが開発した世界初のトランジスタ・ラジオを聴いていた際、「電気の流れをコントロールするトランジスタを利用すれば、無接点のスイッチが作れるかもしれない」とひらめいた。
こうして立石氏は1958年、創業25周年の記念式典において、研究部に対し、「5年以内に、トランジスタを使った“無接点スイッチ”を開発するように」との指令を下した。日本においてオートメーションが普及するよりも早く開発を行うことで、他社に先行して市場を制するという意図があった。
開発には、「七人の侍」と称された優秀な若手研究員が取り組んだ。当時、トランジスタと言えば、ラジオや無線に使うのが一般的で、電気制御を行うスイッチに応用しようとしたのは、立石氏が初めてであった。
前例がないなか、手探りの状態からの開発にもかかわらず、研究員たちはわずか2年で“無接点スイッチ”を完成させた。立石氏の仮説通り、この製品は金属同士が触れ合わないことによって、耐久性が従来の製品の何千倍にも引き上げられており、半永久的に使用できるようになった。
“無接点スイッチ”の開発は、制御分野の技術革新として、国際見本市でも大きな反響を呼んだ。本製品を武器に、立石氏は本格的にオートメーション市場に進出。自社の売上を7年で70億円から400億円へと約6倍に伸ばした(いずれの額も現在の貨幣価値に換算)。
立石氏はその後も、自動券売機、紙幣両替機、ATM、自動改札機など、オートメーションに関する製品を次々と発明。オムロンの基礎を築いていったのである。
10年もの間、業績横ばいだった専門商社。スカウトで獲得した1人の営業マンによって売上3割増に成功!
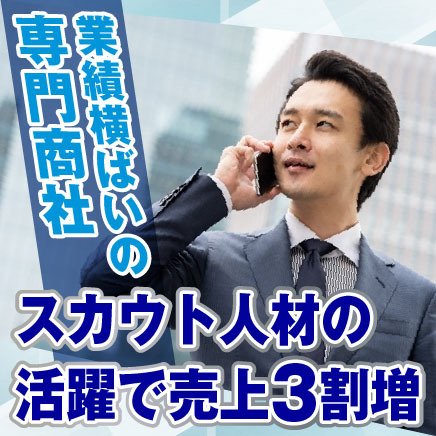
株式会社合田化学(仮名)は神奈川県川崎市に本社を構え、化学工業製品を中心に取り扱っている専門商社だ。創業は1968年。国内にとどまらず、韓国やマレーシアにも倉庫や拠点を持ち、グローバルに展開している。工業薬品、食品添加物、ガラス、セメントなど幅広い商品を国内外から仕入れられることが、同社の強みである。
クライアント情報
- 事業概要
- 化学工業製品の専門商社
- 売上高
- 20億円~
- 経常利益
- 5000万円~
- 上場市場
- 未上場
- 設立年
- 1960年代
- 従業員数
- 30名~
合田化学が創業50年の節目を迎えた2018年、二代目の社長に就任した合田憲之(仮名)は、「ここ10年間、15億円前後で伸び悩んでいる売上を、2023年までに30億円とする」という目標を掲げた。
しかし、今の延長線上で事業を展開していては、目標達成など夢のまた夢だ。営業部隊を率い、かつ自身でも業績に貢献できるような優秀なプレイングマネージャーが不可欠だが、そうした人材は社内におらず、イチから育てている時間もなかった。
合田は、人材紹介会社や求人媒体を駆使して採用活動に注力したものの、即戦力となる人材はそう簡単に見つかるものではない。特に合田化学では、海外から輸入する商材が多いため、特殊な原料に関する広範な知識のほかに、輸入業務についての知見や、海外企業との交渉力など、社員には高い能力が求められた。
「このまま従来の方法で採用を試みても埒が明かない。どうすれば、優秀な人材と接触できるのだろうか……」
いつまでも難航する採用活動に、合田は焦りを募らせた。
候補者 須藤氏(仮名)について
- 年齢
- 40代(当時)
- 年収
- 1000万円(当時)
- 住所
- 東京都世田谷区
- 前職
- 工業薬品の専門商社
そうした中でレイノスから紹介されたのが、須藤正樹(仮名)だ。彼は大学を卒業後、工業用の試薬を扱う専門商社に入社。以来20年間にわたって営業として活躍してきた。その成績は、入社5年を過ぎた頃から、約50名いる営業部員の中で常にトップクラスを誇っており、一目置かれる存在だった。
だが、同社は数年前から、医療用の試薬に注力する方向へと舵を切り、須藤が得意とする工業薬品分野の予算や人員は縮小され始めていた。
「この会社に居続けても、工業薬品の分野で築いてきた人脈やノウハウを活かす機会は少なくなっていくだろう。それならば、より自身の経験やスキルを求めている企業に移った方が貢献できるのではないか」
このように、自社で働き続けることへの不安が徐々に高まりつつあった須藤。レイノスから声がかかったのは、ちょうどそんな頃のことだった。そして、工業薬品を扱っている合田化学に興味を持ち、社長の合田との面談に至ったのである。
須藤と直接話した合田は、すぐ彼に好印象を抱いた。
「言動や立ち居振る舞いから、真面目で実直な方だと分かりました。新卒で入社してから20年間にわたって同じ企業に勤め、かつコンスタントに申し分のない実績を残しておられる。これは、自身の能力を高めようと地道に研鑽を積まなければ成し得ないことでしょう」(合田)
一方の須藤も、「合田化学ならば、得意とする工業薬品の分野で、スキルを活かした仕事ができる」と確信。何より、自身の力が必要とされていることを強く感じた。合田化学は前職より規模の小さい企業ではあったものの、その方が大きな裁量権を得られる可能性が高く、挑戦し甲斐があると考えた。
慣れ親しんだ工業薬品以外の商材にも挑戦
こうして合田化学に入社した須藤は早速、これまで培ってきた工業薬品の知識と営業力を活かし、顧客の要望に応えていった。既存の顧客である民間企業や大学と良好な関係を築き、従来は取引のなかった薬品についても積極的に提案。これまで提供してきた商品とは別に、年間6000万円分の契約を受注した。
また、人脈を駆使した新規営業も進め、自動車部品メーカーや繊維メーカーなど、大手企業を含む5社の開拓に成功。新たに取引先として加わったこれらの会社との契約だけで、年間2億円以上の売上貢献を果たした。
こうして工業薬品の分野で成果を上げた須藤は、食品商材も担当することになった。彼は入社当初、工業薬品以外に携わることを想定してはいなかったが、担当者がやむを得ない理由で退職することとなり、急遽任されたのである。ここには「工業薬品に留まらず、扱う商材の幅を広げて自身の営業経験を積んでほしい」という合田の思いもあった。
須藤が担当することになった商材は「寒天」の原料である「天草」。これまで食品を扱う機会などなかった彼は、天草という商材の特性や用途を知るところから始めた。そして、従来から取引のあった食品会社だけでなく、新規で「ところてんメーカー」への販路拡大を図り、年間3000万円の売上につなげたのである。
「どの商材を仕入れて、どこに販売するか、イチから自分で考えて動いています。大きな裁量権を与えていただき、ありがたいと思っています」(須藤)
合田は、そんな須藤の順応性やチャレンジ精神を高く評価している。
「須藤さんは前職での仕事のやり方に固執せず、弊社に馴染もうとしていることがよく伝わってきます。また、どんなに難しい問題が立ちはだかっても、まずは『どうすれば解決できるか』を考えるという姿勢なので、頼もしい限りです」(合田)
売上30億円の目標達成は射程圏内
須藤は、合田化学でさらなる貢献を果たそうと意気込む。
「関東圏の化学工業や自動車関連の企業を中心に、これまで以上に新規営業に注力したいと思っています。2021年度には全社の売上が20億円に乗るのは間違いありません」(須藤)
これに対し、合田も「今後も新たな商材に挑戦してもらいたいと考えています。どのような商材でも扱える商社マンとして、営業部を牽引する人材になってほしい」と期待を寄せる。彼は近い将来、須藤に営業部のマネジメントや後進の育成も任せるつもりだ。
いまや合田化学の営業部にとって無くてはならない存在となりつつある須藤。その活躍によって、「2023年までに売上30億円到達」という目標は射程圏内だ。ゆくゆくは売上50億円を目指す。高い目標を掲げ、達成に向けて邁進する同社の未来は明るい。
<終>
【スカウト候補者一覧】逆境を覆し成果を残し続ける猛者たち
『レイノス』がこれまでお会いしている候補者について、情報共有いたします。
もし、詳細をお聞きになりたい場合、右上の電話マーク、もしくはメールにてお問い合わせくださいませ。
■候補者 酒井浩介 氏(仮名)
- 所属企業
- ハウスメーカー
(売上高:2000億円~) - 部門
- リフォーム事業部
- 役職
- 課長クラス
- 年齢
- 38歳
- 年収
- 1000万円
●約350名の営業担当者の中で、常に上位5%以内の業績を残している。
●中途入社でリフォーム事業部に配属された後、自身が管掌する課の営業利益率を2年で5ポイント(16%→21%)向上させた。
■候補者 和田光恵 氏(仮名)
- 所属企業
- 人材派遣
(売上高:1000億円~) - 部門
- 営業部
- 役職
- 課長クラス
- 年齢
- 36歳
- 年収
- 800万円
●昇進・昇給スピードは、同期約80名中2位で女性としては最速。
●東京都中央区の大口顧客を担当しており、全国の営業担当者400名のうち、常に上位10%以内の業績を残している。
●現在は育児と仕事を両立しており、女性のキャリアモデルとして、採用説明会や会社のパンフレットなどで取り上げられている。
■候補者 宮崎裕司 氏(仮名)
- 所属企業
- 携帯小売店
(売上高:100億円~) - 部門
- 営業部
- 役職
- 課長クラス
- 年齢
- 35歳
- 年収
- 900万円
●全国に1000名いる販売員の中で常に上位10%以内の実績を残している。
●100名の同期の中でトップクラスの昇進・昇給スピード。
●現在は関西で約10店舗を管掌しており、同氏が担当するエリアの売上は前年比50%、利益は前年比80%伸長した。
■候補者 横山明史 氏(仮名)
- 所属企業
- ディスカウントストア
(売上高:1000億円~) - 部門
- 商品部
- 役職
- 係長クラス
- 年齢
- 34歳
- 年収
- 700万円
●バイヤー就任当初から生鮮食品を担当。日次で数値分析を行い、1什器あたりの粗利を管理。商品構成の見直しも実施し、2年間で担当部門の粗利を120%に引き上げた。
●現在は仕入れと棚割業務に加えグロサリー部門の統括も担っている。50店舗を担当しており、担当店舗全体で売上を前年比140%、粗利を前年比120%に伸ばした。
■候補者 安藤咲良 氏(仮名)
- 所属企業
- 飲食チェーン
(売上高:100億円~) - 部門
- 店舗運営部
- 役職
- 店長
- 年齢
- 28歳
- 年収
- 500万円
●店長に就任後、担当店舗の営業利益率を1年で7%から11%に引き上げた。
●顧客の少ない曜日と時間帯を調査し、人員配置を見直した。その結果、1ヶ月あたりの総労働時間を前年比10%削減した。
●同期40名のうち、最速で店長に昇進。
■候補者 宮本泰三 氏(仮名)
- 所属企業
- 物流業
(売上高:500億円~) - 部門
- 物流センター
- 役職
- 部長クラス
- 年齢
- 42歳
- 年収
- 1200万円
●同社が全国に有する60拠点のなかで、最大の物流センターを統括していた実績を持つ。
●歴代最年少で部長に就任。
●現在は、2000坪の倉庫2ヶ所および1000坪強の物流センターの責任者を務めている。
■候補者 大野達実 氏(仮名)
- 所属企業
- 物流業
(売上高:100億円~) - 部門
- エリア統括部
- 役職
- 課長クラス
- 年齢
- 44歳
- 年収
- 800万円
●配車管理と運行管理に携わりながら、顧客に対する3PL提案も手がけていた。
●教育制度の構築に注力しており、リーダーやマネージャーを輩出することで担当エリアの役職者比率を5ポイント引き上げた。
●現在はエリア統括として営業所8拠点のマネジメントを手がけており、担当エリアの売上を3年で15億円から20億円へと拡大させた。
■候補者 小島徹也 氏(仮名)
- 所属企業
- 電気工事業
(売上高:1000億円~) - 部門
- 工事部
- 役職
- 係長クラス
- 年齢
- 39歳
- 年収
- 1100万円
●1級電気工事施工管理技士の資格を持ち、電気工事の施工管理に従事している。
●主な担当プロジェクトは、大手ゼネコンが手がける20億円規模の大型マンション。
●40階建てのタワーマンションの工事現場で副所長を務めた経験もある。
■候補者 桃田圭介 氏(仮名)
- 所属企業
- 運送業
(売上高:1000億円~) - 部門
- 営業部
- 役職
- 課長クラス
- 年齢
- 34歳
- 年収
- 800万円
●同社において最年少の課長として課を持ちつつ、自身もプレイングマネージャーとして従事している。
●全営業担当者200名中、常に上位3%以内の営業成績を誇り、個人で年間1億円以上の粗利を創出。
●課全体で年間予算50億円を担い、機械メーカーを中心に物流の改善提案を行っている。
■候補者 松川勇斗 氏(仮名)
- 所属企業
- 精密機器メーカー
(売上高:1000億円~) - 部門
- 営業部
- 役職
- 課長クラス
- 年齢
- 37歳
- 年収
- 1500万円
●タイ、マレーシアにおける新規営業を担当しており、現地法人の立ち上げも経験。日系企業への営業活動に加え、現地における営業担当者の育成、マーケティングなども行っている。
●海外に赴任した初年度に、現地法人の売上を前年比200%に伸長させた。
●国内で営業を行っていた頃は、全営業担当者150名中、上位5%以内の営業成績を残していた。
■候補者 中丸和樹 氏(仮名)
- 所属企業
- 携帯販売会社
(売上高:500億円~) - 部門
- au事業部
- 役職
- 課長クラス
- 年齢
- 33歳
- 年収
- 800万円
●エリアマネージャーとして10店舗を統括しており、2年間で担当エリアの店舗数を1.5倍、売上を2倍、営業利益を2.3倍に伸長させた。
●同社の課長としては最年少で、他の課長は全員40歳以上。
■候補者 小野修一郎 氏(仮名)
- 所属企業
- 通信機器販売
(売上高:1000億円~) - 部門
- 営業部
- 役職
- 係長クラス
- 年齢
- 32歳
- 年収
- 900万円
●入社3年目以降、営業成績は常に上位5%以内。
●同期100名中、昇進・昇給スピードはトップクラス。
●現在は、10名の部下を持つプレイングマネージャーとして従事している。同社の係長20名中、昨年度の実績は1位。
■候補者 大石恭也 氏(仮名)
- 所属企業
- 証券会社
(売上高:500億円~) - 部門
- 法人営業部
- 役職
- 係長クラス
- 年齢
- 31歳
- 年収
- 1000万円
●同氏が管掌するチームは、直近の4四半期のうち、3四半期で営業目標を達成している。(目標達成を果たすチームの割合は、全体の40~50%程度)
●富裕層や上場企業の経営者に対して証券や保険商品を販売。
●同期100名中、最速で係長へ昇格。現在は8名のメンバーをマネジメントしながら、プレイングマネージャーとして従事している。
■候補者 佐々木宏 氏(仮名)
- 所属企業
- 自動車部品メーカー
(売上高:5000億円~) - 部門
- 生産企画部
- 役職
- 次長クラス
- 年齢
- 49歳
- 年収
- 1000万円
●工場内における粉塵対策の推進と、原価の削減による実績が評価され、全従業員5000名中1名が選出される環境賞を受賞。
●国内のみならず、アジア工場の生産統括や北米での新工場立ち上げといった実績も有している。
●IoTの知見があり、工場のデジタル化による生産性改善も行っている。
■候補者 江藤義則 氏(仮名)
- 所属企業
- 鉄鋼メーカー
(売上高:1兆円~) - 部門
- 製造部
- 役職
- 主任クラス
- 年齢
- 28歳
- 年収
- 600万円
●同期100名中、最速で主任に昇格。金属板や溶接材などを製造する同社において生産技術者として従事している。
●国内工場において、新ラインの立ち上げに携わった経験を持つ。
●現在はライン長として現場の生産管理を行いつつ、スタッフ6名をマネジメントしている。
外出自粛で利用者増の婚活マッチングサービス、1年で市場規模を20%伸ばし600億円に!

外出自粛によって他者と接する機会が減るなか、オンライン上で恋愛や結婚のパートナーを探す“マッチングサービス”が利用者数を伸ばしています。
サイバーエージェント傘下でマッチングサービスを手がける株式会社タップルが行った調査によると、2020年のマッチングサービス市場は前年比22%増の622億円。2026年には1600億円超にまで拡大する見通しです。
コロナ禍において“出会い”を求める消費者の需要を取り込み、新たな事業モデルとして確立されつつあります。
コロナ禍下で利用者が前年比33%増を記録したオンラインサービス
マッチングサービスの1つである「タップル」は、2020年11月の利用者を前年同月比で33%増やしました。社長の飯塚勇太氏は、利用者の広がりから「市民権を得てきた」と手応えを感じています。
マッチングサービス市場はこれまでも継続的に拡大してきましたが、コロナ禍で成長が加速しました。過去のデータを見ると、阪神大震災のような一種の社会不安が生じた際、結婚相談所の入会者数が増加する傾向がありました。同様に、コロナ禍でも恋愛欲求が高まる人が増えているそうです。
新型コロナウイルスの影響によって、リアルでの出会いやデートの機会は減りましたが、マッチングサービスを利用すればオンライン上でお互いを知ることができます。距離による制限も無くなるため、新しい出会いを求めて利用する人が増加しています。
また、マッチングサービス市場が伸長している要因の1つに、広告効果があります。
マッチングサービスは、一部の媒体では広告掲載が認められていません。消費者に「出会い系」と混同され、媒体の信用を損なう恐れがあるからです。
しかし、2020年からGoogleやLINEでマッチングサービスの広告掲載が解禁。YouTubeを始めとする視聴者が多いサービスを集客に活用できるようになり、利用者増につながりました。
テレビ番組で取り上げられることがあるタップルでは、利用者の年齢層が広がっています。従来は結婚相談所を使っていた30代、40代が、番組の視聴をきっかけに利用するケースが増えているそうです。SNSと同様に、利用者の増加にともなってサービスへの信頼性が高まるため、今後の成長が期待されています。
AIによるサービス強化で、さらなる市場拡大を目指すタップル
ただ、マッチングサービス市場には数多くの競合がひしめいています。そこで、タップルは技術に投資することで他社との差別化を図っているそうです。
「他社サービスでは探しているパートナーの条件を利用者が設定して検索する。一方タップルではAI(人工知能)のアルゴリズムを基に、相性が良いと思われる異性を表示する」と社長の飯塚氏は語る。
参考元:オンライン婚活「市民権得た」|日経産業新聞
タップルでは社内のエンジニア20名弱に加え、サイバーエージェント本体にある「秋葉原ラボ」の人材も活用。同ラボはサイバーエージェント内のBtoCサービスにAIを組み込む研究や開発をする組織です。インターネットテレビの「ABEMA」を始めとする他のサービスも研究していますが、タップルに携わっている人が最も多いといいます。
「リクルートの系列会社が行った調査では、恋人がいない人が7割に達するというデータもある」と話す飯塚氏。今後さらに利用者を増やし、市場の成長を促すねらいです。
新型コロナウイルスの影響による外出自粛で、男女の出会いの場として需要を伸ばしているマッチングサービス。
今後、更に普及していくことが予想されます。
コロナ禍下でも業績を伸ばすファナック。産業用ロボット事業への積極投資で機会損失を防ぐ

コロナ禍下で多くの製造企業が打撃を受けるなか、工作機械の制御装置や産業用ロボットを開発するファナックが業績を伸ばしている。
2021年3月期は世界的に設備投資が減少したことから、第3四半期決算の時点では減収減益と苦境に陥っていたが、通期では売上5323億円(前期比4.7%増)、経常利益1195億円(同16.2%増)と増収増益に転じる見込みである。
中国の景気回復が好業績に寄与
ファナックの業績向上に大きく寄与しているのは、中国における設備投資の拡大だ。同国の景気回復の早さはファナックの想定以上で、同社は2021年3月期の純利益を、従来予想していた718億円(前期比2%減)から、一転して882億円(同20%増)に修正した。
この上方修正の裏付けとなるのは、2020年10~12月期における受注高が1705億円(前年同期比43%増)と伸びたことだ。そしてそれは、中国企業に向けた製品の契約額が前年同期の2.7倍に急増した影響である。具体的には、中国政府のインフラ投資を背景に建機や自動車関連の事業が伸びたほか、特に産業用ロボット事業が好調だった。
中国では、アップルをはじめとする米国企業からの受託製造に加えて、ファーウェイやシャオミ、オッポといったメーカーが、高速通信規格「5G」に対応した新型スマートフォンの生産数を増やしている。
また、新型コロナウイルスの影響で在宅勤務が広がり、タブレットやノートパソコンの需要も拡大。これらに使う電子部品の生産速度を上げるため、製造各社では産業用ロボットの追加導入が進んでいる。
国際ロボット連盟会長のミルトン・ゲリー氏は、世界のロボット生産がコロナ前の水準に戻る時期を「2022年か2023年」とみていたが、これが早まる可能性は高い。
生産設備への積極投資が機会損失を防いだ
受注が好調な理由について、ファナック社長の山口賢治氏は「製品の持つ性能の高さに加え、大量の注文をさばけるよう、工場設備に投資してきたことが有利に働いた」と説明している。
同社は米中貿易摩擦の影響が出始めた2018年度に、茨城県・筑波にて産業用ロボットの生産を行う新工場を稼働させた。さらに本社工場(山梨県忍野村)でも、主力となる製品の生産設備を増強してきた。
このような工場や設備の拡張に伴う費用は、ファナックの利益を押し下げる要因となった。しかし、こうして生産能力を高めたからこそ、企業の設備投資への意欲が回復してきた現在、同社は受注の機会損失を防ぐことができている。
ファナックが2021年3月期通期で想定通りの業績を上げるためには、中国で拡大する需要に応じて、的確に製品を供給していくことが重要となるだろう。
月額300円から家具をレンタルできる!試験導入で消費者から好評を博した新サービスを無印良品が全国展開

「無印良品」を運営する株式会社良品計画は、2021年1月15日から家具の定額貸し出しサービスを開始しました。利用者はベッドや机などを1年単位で借りることができ、気に入った商品はそのまま購入することも可能です。
在宅勤務や外出自粛の広がりにより、机や椅子を仕事がしやすいものに交換したり、自宅を模様替えしたりする消費者が増えています。
これまで家具のレンタルは主に新興企業が担ってきましたが、家具の需要増加やSDGs(持続可能な開発目標)の意識の広がりを受けて大手も続々と参入。コロナ禍における新たなサービスとして注目されています。
安価で家具を借りることが可能!消費者のニーズを捉えた新サービス
この貸し出しサービスは、国内の無印良品182店で本人確認書類を提示して申し込むことができます。契約期間は1年単位で、最長4年間です。契約期間の終了時には、家具の返却か契約期間の延長を選択することができるほか、手数料を支払えば買い取ることも可能。今後はネット上での申し込みもできるように準備を進めるといいます。
貸し出しの対象となるのは全て無印良品の商品で、「木製デスク」や「脚付マットレス」など、どのような内装にもなじむ簡素な家具が揃っています。
料金は契約期間と商品によって異なり、契約期間が長いほど1ヶ月当たりの料金は安くなります。例えば、最も料金が安い「ラウンドチェア」(店頭販売価格は税込み1万4900円)を4年間借りる場合、月額料金は300円です。
同社が定額サービスの本格展開に踏み切ったのは、2020年7月から約3ヶ月間、国内7店舗で試験的に実施した同様のサービスが好評だったためです。昨年は椅子や机をセットにしていましたが「必要な物だけ借りたい」という消費者の声に応えて単品での貸し出しに切り替えたといいます。
大手も参入し始めた家具レンタル、同じ家具を再利用できる利点も
これまで家具の定額貸し出しサービスは、主に新興企業の株式会社サブスクライフや株式会社クラスが手がけてきました。ただ、長引く新型コロナウイルスの影響で、場所にとらわれない働き方や、外出を控えて家の中で生活する「家ナカ」に改めて注目が集まっており、大塚家具などの大手も取り組みを始めています。
また、SDGsの観点からも家具の貸し出しサービスは注目されています。一般的に不要となった家具は、廃棄するか、所定の金額を払って買い取り業者などに回収してもらう必要があります。
一方、貸し出しサービスであれば、新生活や家族構成の変化に合わせて柔軟に家具を変えることが可能です。利用者が返却した家具は補修されて新たな借り手の元に送られるため、資材の節約にもつながります。
「良品計画の執行役員、松岡朋子氏は『長引くコロナで新しい暮らしや働き方が常態化し、持続可能な事業への意識も広がった。サービスで消費者の新生活を支えたい』と話します」
参考元:無印、家具レンタル本格展開|日経MJ
栃木県を除く10都府県では緊急事態宣言の1ヶ月間の延長が決定するなど、新型コロナウイルスの影響は収束の目処が立ちません。
家具の定額貸し出しのような“新常態”に合わせたサービスは、今後さらに広がっていくことでしょう。
【紹介可能な顧問一覧】コロナ禍を乗り切るうえでの強力なパートナーたち
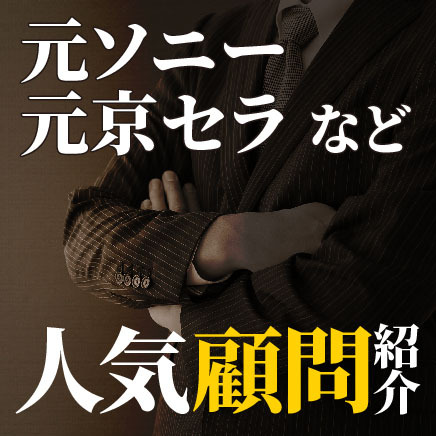
※すぐにご紹介いたします。詳細をお聞きになりたい場合、右上の問い合わせボタンよりご連絡ください。(電話、メール、いずれも対応可能です)
■顧問 中田宗則 氏(仮名)
- 出身企業
- 京セラ株式会社
- 最終役職
- 執行役員クラス
- 年齢
- 60~70歳
- 支援内容
- 工場の生産性改善、人脈を活用した販路開拓
■顧問 和田浩一郎 氏(仮名)
- 出身企業
- 伊藤忠商事株式会社
- 最終役職
- 取締役クラス
- 年齢
- 60~70歳
- 支援内容
- 人脈を活用した販路開拓、営業部隊強化、仕入先の選定
■顧問 脇谷亮治 氏(仮名)
- 出身企業
- ソニー株式会社
- 最終役職
- 取締役クラス
- 年齢
- 50~60歳
- 支援内容
- 海外展開支援
■顧問 桃井公平 氏(仮名)
- 出身企業
- 船井電機株式会社
- 最終役職
- 取締役クラス
- 年齢
- 60~70歳
- 支援内容
- 事業戦略の策定、経営指導
■顧問 長谷川平次 氏(仮名)
- 出身企業
- 森永製菓株式会社
- 最終役職
- 取締役クラス
- 年齢
- 70~75歳
- 支援内容
- 食品業界のマーケティング戦略立案、中国進出、経営指導
■顧問 羽田進 氏(仮名)
- 出身企業
- キヤノンマーケティングジャパン株式会社
- 最終役職
- 取締役クラス
- 年齢
- 70~75歳
- 支援内容
- 営業部門強化
■顧問 深瀬幸三 氏(仮名)
- 出身企業
- シャープ株式会社
- 最終役職
- 取締役クラス
- 年齢
- 60~70歳
- 支援内容
- 人脈を活用した販路開拓、技術開発、社外取締役
■顧問 角田勲 氏(仮名)
- 出身企業
- キリンビールホールディングス
- 最終役職
- 取締役クラス
- 年齢
- 60~70歳
- 支援内容
- 人脈を活用した高級ホテル・食品メーカー・外食企業への販路拡大
■顧問 井口肇 氏(仮名)
- 出身企業
- ダイハツ工業株式会社
- 最終役職
- 取締役クラス
- 年齢
- 65~70歳
- 支援内容
- 人事制度の構築、経営指導
■顧問 秋田稔 氏(仮名)
- 出身企業
- ユニリーバ・ジャパン株式会社
- 最終役職
- 取締役クラス
- 年齢
- 65~70歳
- 支援内容
- ヘアケア・スキン製品の新商品開発、工場の生産性改善、品質保証体制の強化