経営者向け情報【2月21日更新】
今月号の目次
生産性を3倍に高める次世代の板金加工機が登場!設備投資に活用できる最大1億円の支援制度も

生産性を3倍に高める板金加工機の新開発によるDX化の推進が、中小企業の人手不足問題に応えます。
次世代の板金曲げ機を活用することで初心者も即戦力に
板金加工機で国内シェア7割を占め、世界でも大手の株式会社アマダは、人手不足の解消につながる次世代の板金曲げ機(ベンディングマシン)を今年中に実用化すると発表しました。AIが金型の選定や精密な作業を自動化し、従来機より生産性が3倍に向上するとしています。
幅4メートル、高さ3メートルのベンディングマシンは、上下2つの金型で金属の板を挟み、折り曲げます。
作業員の顔の前にモニターがあり、AIにより「腰折れしないよう曲げ速度を落としてください」といったきめの細かい加工の助言が可能。板金は10ミクロン押すだけで、仕上がりの角度が1度変わる場合もあり、同業界にとって画期的な工作機械といえそうです。
モニターはカメラ映像と、赤色で作業ポイントを示す拡張現実(AR)の合成を映しだします。音声で曲げの位置や速度を指示できるため、同社は「初心者も即戦力になる」と説明します。
板金加工品の用途はATMや自動販売機、コピー機、厨房設備と幅広く、EVの電池ケース、充電設備、半導体製造装置向けなどニーズも増える見込み。次世代機の発売が待たれます。
熟練度に合わせた操作画面やプログラムが起動し、15カ国語に対応
従来の機械では、まず作業員が完成図面から最適な金型や加工手順を考え、加工機にプログラムを入力します。その後、主に「段取り」「試し曲げ」「加工」の3つの工程で完成させます。段取りでは、上下でそれぞれ100本以上から最適な金型を選び、設置します。金型の重さは、20kg超の場合もあり重労働です。
次の工程は、初心者が最も時間のかかる試し曲げです。板金は曲げても元に戻る力が働くため、入念なテストが必要。固定位置や力加減、仕上がりの計測などは経験値がスピードを左右します。全体の作業時間のうち、実際の「加工」は2割で、一連の準備に8割を要します。
今夏ごろにまず日本で発売する次世代機は、AIが熟練工の経験値や材料のデータを学習します。図面をスキャナーで読み込み、最適な金型や加工を判断し、プログラムを自動で作成。金型ラックのある上位機種は金型の選択、運搬、設置まで全自動で行うため、作業者の負担も軽くなります。
試し曲げでは、AIが材料の情報を学ぶことで精度が向上。センサーが自動で仕上がりの角度を示すため、寸法の計測は不要です。加工はARや音声の指示に沿って行います。次世代機は1台で、熟練工3人が従来機3台でこなす作業量を処理し、初心者でも2週間ほどの研修で操作できるようになるそうです。
例えば4枚の金属板でつくる30cm四方のパソコン向け精密板金部品の場合、初心者は従来機での段取りから試し曲げ、加工までに計80分かかりました。熟練工は40分でこなせますが、次世代機の実証ではわずか20分足らずで完了したといいます。
株式会社アマダの社長、磯部任氏は「製造業の質を支えてきた熟練工が減り、加工機で効率化や自動化をキーワードにした大きな進化が不可欠だ」と話しています。
次世代機は顔を認証し、熟練度に合わせた操作画面やプログラムが起動します。15カ国語に対応していることから、外国人労働者でも使用することが可能です。また動力源が油圧から電動に変わっており、CO2排出量を最大20%減らすことができます。
アマダは、本社に「グローバルイノベーションセンター」を新設し、板金や切削など90種類の最新機をそろえ、顧客が使い勝手や品質を検証できるようにしました。
次世代機の価格は1台数千万円の従来機より15%ほど高い見通しですが、抜本的な解決に注力できます。24年から欧米でも販売し、25年度に世界販売で現状比25〜50%増の2500〜3000台を計画しています。
【東京都】第5回 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業
ここからは、東京都の中小企業を対象に、機械設備の新たな導入で経費の一部が助成される「第5回 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業」をご紹介します。
人手不足の解消に向け、行政の支援を受けて最新技術を取り入れることができないか、調べてみることをお勧めします。
●「躍進的な事業推進のための設備投資支援事業」とは
DXの推進、都市課題の解決に貢献し、国内外において市場の拡大が期待される産業分野で機械設備等を新たに導入するための経費の一部が助成されます。機械設備は、機械装置・器具備品・ソフトウェアに該当するものです。
●どんな企業が対象か?
東京都に拠点を有する中小企業または小規模企業者のうち、下記のいずれかの条件を満たす企業。
(1)競争力・ゼロエミッション強化
競争力強化を目指した事業展開に必要となる機械設備、または、事業の省エネを実現するために必要となる機械設備を新たに導入する。
(2)DX推進
デジタル技術を活用した新しい製品・サービスの構築や、既存ビジネスの変革を目指すため、機械設備を新たに導入する。
(3)イノベーション
市場拡大が期待される産業分野において、都市課題の解決に貢献する革新的な商品やサービスを創出するため、機械設備を新たに導入する。
(4)後継者チャレンジ
事業承継を契機として、後継者による事業多角化や新たな経営課題の取り組みに必要な機械設備を新たに導入する。
●どのような補助を受けられるか?
・競争力、ゼロエミッション強化:対象経費が200万円以上2億円未満の場合はその2分の1、対象経費が2億円以上の場合は最大で1億円まで支給。
・DX推進、イノベーション、後継者チャレンジ:対象経費が150万円以上1億5000万円未満の場合はその3分の2、対象経費が1億5000万円以上の場合は最大で1億円まで支給。
●ポイント
募集開始は4月上旬頃の予定。
●申請についての問い合わせ先
公益財団法人東京都中小企業振興公社 設備支援課
TEL: 03-3251-7884
【スカウト候補者一覧】製造業において好業績を牽引するスカウト候補者20名
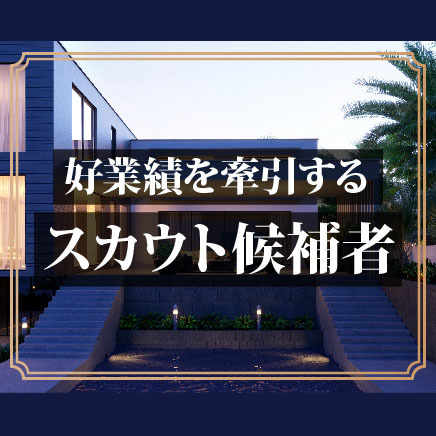
サーチ型スカウトを手がける『レイノス』だからこそ接触できた候補者について、情報共有いたします。今週ご紹介するのは、当社がお会いしたビジネスパーソンのうち、製造業において活躍している20名です。
詳細は、右上の電話マーク、もしくはメールにてお問い合わせくださいませ。
■候補者 吉村隆治 氏(仮名)
- 所属企業
- 精密機器メーカー
(売上高:2000億円~) - 部門
- 海外事業部
- 役職
- 事業部長クラス
- 年齢
- 56歳
- 年収
- 1500万円
●赤字を発生させていた海外事業部において、市場分析、販売戦略の見直し、徹底したコスト管理などを実施。大幅な黒字化を実現し、損益分岐点比率50%の収益体質を構築した。その結果、同事業部はリーマンショックにおいても黒字を維持することができた。
●工場にて、作業員1人あたりの労働生産性を1年で2.5倍に改善。工場の人員規模を2年で5倍に成長させた。
■候補者 佐々木宏 氏(仮名)
- 所属企業
- 自動車部品メーカー
(売上高:5000億円~) - 部門
- 生産企画部
- 役職
- 次長クラス
- 年齢
- 49歳
- 年収
- 1000万円
●工場内における粉塵対策の推進と、原価の削減による実績が評価され、全従業員5000名中1名が選出される環境賞を受賞。
●国内のみならず、アジア工場の生産統括や北米での新工場立ち上げといった実績も有している。
●IoTの知見があり、工場のデジタル化による生産性改善も行っている。
■候補者 浜本雄司 氏(仮名)
- 所属企業
- スポーツ用品メーカー
(売上高:100億円~) - 部門
- 商品開発部
- 役職
- 部長クラス
- 年齢
- 52歳
- 年収
- 1100万円
●ゴルフ、スキー、フィットネスなどに使用する商品の企画・開発に30年以上携わってきた。
●入社9年目に同期トップクラスのスピードで課長に昇格し、以来もマネージャーとして組織を牽引。現在は事業部長として企画・開発・生産・生産管理を一貫して担う組織で70名のメンバーを管掌している。
●プライベートブランド商品の企画から、生産管理、ブランド構築まで一貫して担うことができる。
■候補者 谷本拳 氏(仮名)
- 所属企業
- 鉄鋼メーカー
(売上高:5000億円~) - 部門
- 製造部
- 役職
- 課長クラス
- 年齢
- 46歳
- 年収
- 1000万円
●責任者として中国での工場立ち上げに携わった実績を有する。
●課長への昇進は同期で最速。鋼管を手がける同社において、製造業務を経験後、生産設備の開発に従事していた。
●現在は工場長としてスタッフ50名を管掌。工場の生産コストを3年で15%引き下げた。
■候補者 倉持篤司 氏(仮名)
- 所属企業
- 生活用品メーカー
(売上高:1000億円~) - 部門
- 研究開発部
- 役職
- 次長クラス
- 年齢
- 43歳
- 年収
- 1000万円
●植物や食物に関する学術的な知見に加え、製造委託先との折衝、AIアプリを活用したビジネスの構築など幅広い経験を有する。
●育毛剤、錠剤の剤形、舌の画像からAIで口臭リスクや健康状態を予測するシステムなど、様々な開発実績があり、登録特許は約60件にのぼる。
●細菌培養、細胞培養、遺伝子解析、動物実験、HPLCといった、生化学実験に関する基本的な知識、技術も保有。
■候補者 堀正孝 氏(仮名)
- 所属企業
- 精密機器メーカー
(売上高:2000億円~) - 部門
- 営業部
- 役職
- 課長クラス
- 年齢
- 36歳
- 年収
- 1000万円
●新卒として入社後、一貫して法人営業に従事。入社5年目には年間粗利3億円という実績で全営業担当者200名中1位に輝いた。
●現在はプレイングマネージャーとして、部下30名をマネジメントしながら営業を続けている。
■候補者 橋田悠介 氏(仮名)
- 所属企業
- 自動車部品メーカー
(売上高:3000億円~) - 部門
- 工機部
- 役職
- 課長クラス
- 年齢
- 45歳
- 年収
- 1000万円
●使用者の技術に関わらず、安定した品質の金型加工データを作成できるシステムを開発。これにより、金型の生産量は前年比40%増となった。
●全社のデジタル化を推進。間接部門において紙の書類管理や役職者の押印待ちにかかる時間を削減したことで、該当部署の業務時間を30%短縮した。
■候補者 高山透 氏(仮名)
- 所属企業
- 飲料メーカー
(売上高:1000億円~) - 部門
- 営業部
- 役職
- 課長クラス
- 年齢
- 38歳
- 年収
- 1000万円
●ブラジルやメキシコといった、南米で販路開拓を手がけた経験がある。商品の特性上、日本からの輸送が難しかったため、現地生産のための工場設立にも携わった。
●南米で現地の人材を採用して活用。拠点の売上を1年で60%伸長させた。
●同期50名のうち最速で課長に昇進。現在は帰国しており、赤字拠点の立て直しを担っている。
■候補者 斉藤基樹 氏(仮名)
- 所属企業
- 精密機器メーカー
(売上高:2000億円~) - 部門
- 営業部
- 役職
- 課長クラス
- 年齢
- 36歳
- 年収
- 900万円
●部下30名をマネジメントしながら、プレイングマネージャーとして従事。
●入社5年目に年間粗利4億円という実績で全営業担当者250名中1位に輝く。
●昇進・昇給スピードは同期150名中トップクラス。
■候補者 岡崎鉄次 氏(仮名)
- 所属企業
- 光学機器メーカー
(売上高:500億円~) - 部門
- 設計部
- 役職
- 課長クラス
- 年齢
- 44歳
- 年収
- 900万円
●機械設計はもちろん、生産技術や品質管理など幅広い知見を有しており、フィリピンやインドネシアといった海外の生産工場での量産化を手がけた経験もある。
●3D-CADの導入を担当し、他部門へも展開。これにより、開発期間の4ヶ月短縮、品質事故の発生率15%低減といった業務改善が実現した。
●現在は新製品開発のトップであるプロダクトマネージャーとして、10名程の部下を管掌している。
■候補者 大宮連次 氏(仮名)
- 所属企業
- 加工食品メーカー
(売上高:1000億円~) - 部門
- 海外営業部
- 役職
- 課長クラス
- 年齢
- 45歳
- 年収
- 900万円
●主にヨーロッパ向けの販売を手がけ、フランスやイギリスでの支店立ち上げに貢献。各国に合わせた商品パッケージにするためのデザイン変更にも携わった。年間6億円程の予算を担っている。
●入社から2年間は国内での営業活動に従事。商談の際に販促キャンペーンのアイデアなどを披露する企画提案型の営業を行い、年間5000万円~1億円の売上を作っていた。
●課長への昇進スピードは同期30名中で最速。
■候補者 竹島正和 氏(仮名)
- 所属企業
- ゴム製品メーカー
(売上高:1000億円~) - 部門
- 技術開発部
- 役職
- 課長クラス
- 年齢
- 42歳
- 年収
- 900万円
●コンベヤベルトの研究・開発に従事。摩耗のメカニズムを解析して、製品の耐用期間を伸ばすための研究結果を本部に提出した。
●使用環境を考慮して、最適な原料の配分率を割り出すプログラムを開発。年間で数千万円に相当するコスト改善効果を上げた。
●中国工場における生産性改善プロジェクトや、ドイツ、マレーシア、インド、アメリカなどの販売会社での技術トレーニングを実施した経験があり、海外での活動実績も豊富。
■候補者 竹田行春 氏(仮名)
- 所属企業
- 大手飲料メーカー
(売上高:3000億円~) - 部門
- 海外営業部
- 役職
- 課長クラス
- 年齢
- 38歳
- 年収
- 900万円
●入社から7年間は国内営業を担当。営業成績が認められ、同社の主要顧客(大手量販店など)を任される。
●2015年より、海外営業部に配属。中国、東南アジア向けの販売を手がけ、タイ(バンコク)、インドネシア(ジャカルタ)での支店立ち上げを実現させる。
●課長への昇格スピードは同期25名中、最速。
■候補者 設楽雅紀 氏(仮名)
- 所属企業
- 精密機器メーカー
(売上高:1000億円~) - 部門
- 営業部
- 役職
- 係長クラス
- 年齢
- 31歳
- 年収
- 800万円
●同期80名中、トップで係長に昇格(入社7年目)。
●入社6年目に全国の営業マン200名中、トップの成績を残す(年間粗利3.5億円)。
●現在は、メンバー12名を率い、プレイングマネージャーとして従事。
■候補者 白木鉄二 氏(仮名)
- 所属企業
- 飲料メーカー
(売上高:5000億円~) - 部門
- 海外営業部
- 役職
- 課長クラス
- 年齢
- 41歳
- 年収
- 900万円
●国内の中小企業をメインターゲットとして新規営業に5年間従事。6年目から海外営業部で勤務し、主にインドネシアやタイなど、アジア向けの販売を手がける。各国の法規制に合わせた商品開発などを実施し、現地法人の立ち上げも経験している。
●昇進・昇給スピードは同期30名のうち最速。同氏の管掌する支店は、5年連続で売上が前年比20%以上伸長している。
■候補者 藤本徹 氏(仮名)
- 所属企業
- 加工食品メーカー
(売上高:3000億円~) - 部門
- 海外営業部
- 役職
- 課長クラス
- 年齢
- 42歳
- 年収
- 800万円
●国内の百貨店やスーパーへの新規開拓営業に7年間従事。3年目からは毎年全国の営業マンの上位10%の実績を残していた。
●8年目から海外営業部で勤務。主に北米やカナダなどへの販売を手がける。現地の支店立ち上げも経験。同氏が管掌する支店は3期連続で売上が20%以上伸長している。
●課長への昇格スピードは同期40名のうち最速。
■候補者 武井淳平 氏(仮名)
- 所属企業
- 測定機器メーカー
(売上高:1000億円~) - 部門
- 研究開発本部
- 役職
- 係長クラス
- 年齢
- 38歳
- 年収
- 800万円
●業界でトップシェアを誇る精密測定機器の研究・設計を手がけている。
●同氏が携わった研究によって、過去15年間で10件の特許を取得し、6種類の商品が開発された。同氏の功績により、売上が年間150億円、粗利が年間30億円生まれている。
■候補者 井原晴太 氏(仮名)
- 所属企業
- 自動車部品メーカー
(売上高:100億円~) - 部門
- 製造部
- 役職
- 係長クラス
- 年齢
- 34歳
- 年収
- 800万円
●工場において、マシニングセンターのプログラム入力を効率化し、サイクルタイムを20%削減するなどの改善実績がある。
●これまで製造課、生産技術課への配属経験があり、鍛造、切削加工を中心に技術を習得している。
●現在は150名規模の新工場の副責任者として、生産管理、品質管理、生産性の改善を手がけている。
■候補者 高野正史 氏(仮名)
- 所属企業
- 飼料メーカー
(売上高:100億円~) - 部門
- 製造部
- 役職
- 課長クラス
- 年齢
- 41歳
- 年収
- 800万円
●新卒として入社後、一貫して配合飼料の製造に従事。
●従業員20名を管掌しており、工場の生産性向上に注力。製造ラインの新規立ち上げなどにも従事し、3年で生産性を約2倍に引き上げた。
●設備の改良や生産フローの見直しを実施した。その結果、納期の短縮を実現し、年間で5000万円のコスト削減に成功した。
■候補者 江藤義則 氏(仮名)
- 所属企業
- 鉄鋼メーカー
(売上高:1兆円~) - 部門
- 製造部
- 役職
- 主任クラス
- 年齢
- 28歳
- 年収
- 800万円
●同期100名中、最速で主任に昇格。金属板や溶接材などを製造する同社において生産技術者として従事している。
●国内工場において、新ラインの立ち上げに携わった経験を持つ。
●現在はライン長として現場の生産管理を行いつつ、スタッフ6名をマネジメントしている。
【会社名】レイノス株式会社
URL:https://www.raynos.co.jp/
【お問い合わせ(Eメール)】:
matsushita@race-backs.co.jp(担当者:松下)
【お問い合わせ(電話)】:
080-9866-5321(担当者:松下)
「考えるべきはご自身の人生です!」エージェントの一言で現職企業への“恩義”から自身の将来に視線を移し、移籍を決断した若手マネージャー
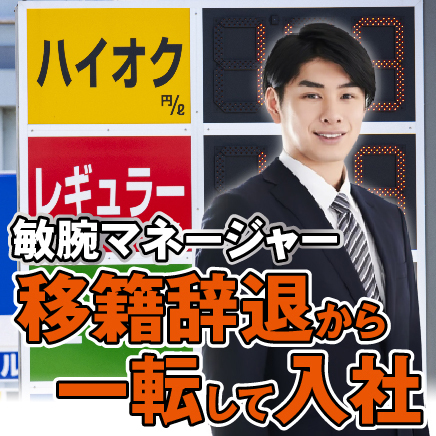
大分県で8店舗のガソリンスタンドを経営している島本石油株式会社(仮名)。毎年、業績は2~3%ながら緩やかに成長していたが、社長の島本健三(仮名)は危機感を抱いていた。会社の将来を担うマネージャーが育っていなかったためだ。
社員に経営学を学ばせようにも、実践力がつくまでには1~2年かかるだろう。また、社内には教育する体制がないため、外部で学ばせるとなると、費用も数百万円はかかる。マネージャーを育てなければ、より大きな成長は見込めないが、人材教育をしている余裕はないという状況に陥っていた。
クライアント情報
- 事業概要
- ガソリンスタンド
- 売上高
- 30億円~
- 経常利益
- 3000万円~
- 上場市場
- 未上場
- 設立年
- 1960年代
- 従業員数
- 50名~
そのような中で、島本がレイノスの赤城哲(仮名)を通じて紹介されたのが、石川和良(仮名)であった。
石川は、当時在籍していたガソリンスタンド運営会社にアルバイトとして入社。販売が上手い先輩を観察し、営業トークを何度も練習することで成績を上げ、正社員に登用された。その後、店長となってからも才覚を発揮。管掌店舗は2店、3店と増えていき、最終的にはエリアマネージャーとして6店舗を任せられていた。
島本石油と同等の店舗数を統括してきた経験のある人材。実績としては申し分ない。島本は早速、赤城に面談の設定を依頼した。
「どのようにして6店舗をまとめあげているのか」「店舗ごとの進捗管理の方法は?」「従業員の育成において心がけていることは何か」――面談の場で、島本が繰り出す矢継ぎ早の質問に対して、冷静かつ的確に回答する石川。島本はその様子に、「彼こそ、今の島本石油に必要な人材だ!」と確信し、移籍のオファーを出した。
■候補者 石川氏について
- 年齢
- 20代(当時)
- 年収
- 700万円(当時)
- 住所
- 大分県大分市
- 前職
- ガソリンスタンド運営会社 エリアマネージャー
一方の石川は、移籍など全く考えていなかった。アルバイト時代を含めて10年近く働いてきた現職企業には愛着があった。また、全社員300名中トップ10に入る業績を上げていた石川は、仕事にやりがいを感じており、待遇にも満足していた。
島本と面談したのは、あくまで赤城から「話だけでも聞いてみませんか。情報収集にもつながります」と言われたためで、元より移籍については断るつもりだったのだ。そして島本のオファーに対し、石川は辞退の意向を伝えた。
自身の人生にとってベストな選択とは何か
エージェントの赤城は、そんな石川のもとへ足繁く通った。赤城が石川と話していて感じたのは、彼が非常に高い成長意欲の持ち主であるということだ。確かに石川は今、現職企業で上位の成績を収めている。周囲から認められ、居心地も悪くないだろう。
しかし、現職企業の業績は売上・利益ともに下降線を辿っており、設備への投資額などを見ても、同社が守りの経営に入っていることは明白であった。遠からず、石川の成長欲は満たされなくなるはずだ。
そこで、赤城は石川に語った。
「確かに今は、現状の給与と待遇でも満足かもしれません。しかし、もし石川さんがこれ以上の成長をお望みならば、現職に留まるべきではないでしょう。これから30代、40代とキャリアを積んでいくことを考えたとき、規模こそ小さくはなりますが、島本石油で社長の右腕としての道を歩まれた方が、ステップアップにつながるとは思いませんか」
これに対し、「申し訳ありません。おっしゃることは分かります。経営者の近くで働いた方が、大きな成長を得られるでしょう。ただ、どうしても10年間お世話になってきた現職への思いを捨てることはできません……」と返した石川。その日の面談は物別れに終わった。
パワポ100枚に及ぶ資料で移籍メリットを説く
次に会った時、赤城は石川が移籍を躊躇している最大の理由である「現職企業への愛着」に焦点を絞って話をした。
「現職に強い思い入れがあるのは理解できます。もちろん、恩義を大切にするのは素晴らしいことです。しかし、石川さんは現職企業で既に大きな実績を残されており、十分に恩は返しているのではありませんか」
そして、こう続けた。
「石川さんの人生を考える上で、現職企業に残ることは本当にベストな選択なのでしょうか。大変失礼ながら、変化の激しい時代にあって、守るばかりの企業に未来はないと思います。石川さん、今回の選択に懸かっているのは、あなたご自身の人生だということを忘れないでください」
この赤城の言葉に、石川もたじろいだ。「そうですね……考えさせてください」。明らかに、石川の心は島本石油への移籍に傾き始めていた。
そして、赤城は最後の一手を打った。石川の現職企業と島本石油を30項目もの指標で比較・分析したデータを、パワーポイント100枚近くに及ぶ資料に落とし込み、定量的な根拠をもとに、改めて石川が島本石油に移籍すべき理由を説いたのである。
その資料では、売上や利益といった基本情報はもちろん、各店舗の立地、競合の状況、今後行われる道路工事の予定まで網羅した上で、島本石油の成長性が述べられていた。その論理的かつ緻密な分析に、石川も思わず唸った。
こうして、島本石油への移籍を真剣に考えるに至った石川。最終的には、再び島本との面談に臨み、それが最後のひと押しとなって、入社することとなった。
自走できる組織をつくる
入社した石川が取り組んだのは、人材育成である。それまで島本石油には研修マニュアルがなく、「OJT」の名のもと、人材教育は現場に任されていた。そこで石川は、島本石油が求める人材を育てるため、入社した従業員にどのような教育を施すのか、研修から作成していったのである。
石川は、現場に漂っていた「仕事をやらされている」という雰囲気の払拭にも努めた。例えば「なぜその業務が必要なのか」から改めて指導したことで、社員の間には仕事に対する納得感が生まれ、その結果、自発的に動く者も出てくるようになった。
これまでは現場を動かす際に細かい指示を出していた島本だが、今では多くの業務を石川に任せている。社員を成長させることで、「社長がいなくても自走できる組織」の構築を目指す考えだ。
石川もそれに応え、「“言われたからやる”ではなく、自身で目標を設定して達成へと努力できるような社員を育成するのが、私の役割です」と語る。
「研修を繰り返して、徐々に現場社員の実力も付いてきた」と手応えを感じている島本と石川。実際に、島本石油の経常利益は石川の入社から1年で前年比120%と成長を遂げた。
そう遠くない未来には、社内からマネージャー層も育ってくるだろう。その希望を胸に、2人はさらなる企業の発展に向けて走り続ける。
<終>
【会社名】レイノス株式会社
URL:https://www.raynos.co.jp/
【お問い合わせ(Eメール)】:
matsushita@race-backs.co.jp(担当者:松下)
【お問い合わせ(電話)】:
080-9866-5321(担当者:松下)
関東大震災で全てを失うも、身一つで再起。シャープ創業者・早川徳次氏に学ぶ不屈の精神

「人が真似するような商品をつくれ」。この名言を体現するかのように、シャープペンシルを始めとする数々の発明品を世に送り出した、シャープ創業者の早川徳次氏。今回は、困難な状況でも諦めずに挑戦した、彼の波乱万丈な人生を辿りたい。
わずか18歳で開業。数々の発明で成功を収める
明治中期の1893年、東京に生まれた早川氏は、幼少期から苦労を重ねた。2歳にもならないうちに他家へと預けられ、そのまま養子となった彼は、8歳にして金属細工店へ丁稚奉公に出ると、金属加工の技術を叩き込まれたのである。
15歳で一人前の職人となった早川氏がまず発明したのが、穴のいらないベルトのバックル「徳尾錠」であった。この斬新なバックルに大量の注文が入ったことで資金を得た早川氏は、自ら金属加工会社を開業。この時、彼はまだ18歳の若さだった。
徳尾錠では成功を収めたものの、「順境はいつまでも続かない」と考えた早川氏は、新製品の開発に余念がなかった。彼が次に発明したのは、水道の蛇口を好きな方向へむけることができる「水道自在器」である。
それまでも同じような製品はあったが、早川氏は水道自在器の取り付け部品を9個から3個に変更。これによって、30分かかっていた取り付け時間がたったの1分で済むようになり、利便性の高さから本製品は飛ぶように売れた。
その他にも、洋傘や文具の部品など幅広く手がけた早川氏。事業が徐々に伸長する中で、作業の効率化を目指して導入したのが「1馬力モーター」である。価格は200円。当時、職人の月給が約10円であったことを考えると、現在の貨幣価値で500~600万円はする代物だった。
それは、早川氏の営む町工場には不釣り合いとも思える高額な設備投資であった。しかし、いずれはモノづくりが機械化されることを見越していた彼は、「先んずれば人を制す」と導入に踏み切った。
部品の製造だけでは飽き足らず、独自の「繰出鉛筆」を開発
こうして業容を拡大させていった早川氏は、生き別れとなっていた兄姉と再会。この出来事が、彼に次の道を与えることとなった。兄が、早川氏に「繰出鉛筆(のちのシャープペンシル)」の部品を作る仕事を持ち込んだのである。
早川氏に求められたのは、あくまで「部品」を作る仕事だったが、彼はこれだけでは満足しなかった。当時の「繰出鉛筆」はセルロイド製の太くて不格好な製品で、壊れやすかったのである。
そこで独自に開発を行い、より書きやすく、壊れにくい「繰出鉛筆」を目指した早川氏。そして、試行錯誤の末、ついに丈夫で美しい金属製の「早川式繰出鉛筆」が完成した。
“逆輸入”で大ヒットしたシャープペンシル
しかし、この製品は当初、全く売れなかった。売り込みに行った文具店からは、「和服に合わない」「金属製は冬に冷たく感じる」など散々な評価を受けたのである。早川氏がそれでも諦めずに売り込みを続けていると、意外なところから大量の注文が入った。それは、横浜にある外国商館からの発注であった。
当時、ヨーロッパは第一次世界大戦の真っ只中。各国同様、ドイツでも製造業が軍需優先を求められたことで、技術力に優れた同国製の「繰出鉛筆」が品薄となり、代替品として高品質な「早川式繰出鉛筆」に白羽の矢が立ったのだ。
そして、欧米市場で人気に火がついた「早川式繰出鉛筆」の噂は日本にも広まり、国内の問屋からも次々に注文が舞い込んだのである。
これを受け、芯を極細にするなど、「早川式繰出鉛筆」にさらなる改良を加えた早川氏。正式名称も「エバー・レディ・シャープ・ペンシル」と改めた。これが、後に社名「シャープ」の由来となるのである。
シャープペンシル事業の急成長に伴い、早川氏は工場を増設。それと同時に、製造の効率化を図るべく、流れ作業の導入や、高性能な輸入機械の設置といった施策を推進。雇用も増やし、従業員は200名を超えた。
関東大震災で何もかも失う
しかし、そんな順風満帆な日々を過ごしていた早川氏を悲劇が襲った。関東大震災である。東京一円で猛威をふるった大火事により、工場は焼失。妻と2人の子どもも失った。そこに追い打ちをかけたのが、早川氏の事業存続が危ういと見た取引先からの、借金の返済要求だった。
「全てを失ってしまった・・・・・・この先、一体どうすればいいのか・・・・・・」
この窮地に、早川氏はやむなく会社の解散を決断。震災の被害を免れた機械類を含め、事業を取引先に譲渡することで、負債を処理する算段を立てた。そして、残った従業員とともに、自らシャープペンシル製造の技術指導を行うべく、譲渡先となった大阪の企業に出向したのである。
しかし、それでも早川氏は、決して事業への情熱を失ってはいなかった。この大阪行きは、言わば再起に向けた準備段階だったのだ。
譲渡先での技術指導を終えると、早川氏は田園地帯が広がるばかりの土地を借り受け、「早川金属工業研究所」を創業した。当面の仕事は文具部品製造が中心だったが、早川氏は再起のため、全く新しい事業を模索。そんな時に出会ったのが、ラジオであった。
外国製品の半額以下。ラジオ事業で復活
ある日、所用で心斎橋に出かけた早川氏は、時計店にアメリカ製の鉱石ラジオが置いてあるのを目にした。「日本でもラジオ放送が開始される」との新聞記事が頭に残っていた彼は「次の事業はこれだ!」と直感。ラジオを購入して社に戻ると、早速、従業員たちとこれを分解して、構造の研究に取りかかった。
従業員たちは、金属加工の技術は持っていても、ラジオについては素人ばかり。それでも彼らは、部品を一つひとつ分解しては、形状や特性を調べ、同じものを再現していった。そして、1年も経たないうちに、自分たちの手で鉱石ラジオを製造することに成功したのである。
時は、大阪でラジオ放送が開始される2ヶ月前。試験放送を受信し、鉱石ラジオの初号機から明瞭な音声が聞こえると、早川氏は従業員たちと抱き合って喜んだ。
早川氏は放送開始の機を逃さず、鉱石ラジオの生産・販売を開始。3円50銭という販売価格は外国製品の半額以下であり、発売するや一気に売れた。
その後も電子レンジ、電子計算機といった商品を次々と開発し、シャープの礎を築いた早川氏。どんな苦難が降りかかろうとも、怯まずに立ち向かった彼の姿勢からは、学べる部分が多いだろう。
売上を5000万円から3億円まで伸ばした刺繍加工会社!アパレル企業向けから一般企業向けへのWeb戦略の転換が成功のカギに

アパレル企業の下請けから一般企業向けに自社サイトの戦略を転換して、売上を5000万円から3億円まで伸ばした刺繍加工会社があります。
大手の指定工場から業績が80%減少して苦境に
株式会社マツブンは、スーツに持ち主の名前を手刺繍する職人として1939年に創業しました。
70年代から90年代にかけてはアパレルブランドのロゴを刺繍する下請け事業で成長。高品質な仕上がりからバーバリーやアーノルド・パーマーといった大手の指定工場に選定されました。パーマーのシンボルである「傘」を刺繍するにあたり、専用の糸の開発もマツブンで手がけたそうです。
株式会社マツブンの3代目である現社長、松本照人氏は、外資系の商社で10年間マーケティングを経験したのち、32歳で家業に入りました。当時のマツブンは業績不振のまっただ中。アパレルブランドの多くは生産拠点を中国に移し、取引先は苦境に陥っていました。
松本氏がマツブンに入社した2000年には、全盛期にあった1億8000万円の売上が4800万円、取引先は15社から3社にまで減っていました。
そこで入社間もない松本氏は、新しい取引先を得ようと飛び込み営業を開始。ワイシャツやニットのメーカーにアポ無しで訪問すると、面会には応じてもらえました。
ただ、肝心の受注については「うちもカツカツ。お願いできる仕事なんてないよ」と断られるばかり。
他にも電話帳をめくって電話セールスをしたり、電信柱広告を出したり、2001年には自力でホームページも作成しました。さらに、検索からサイトに誘導しようと、当時はさほど普及していなかったグーグルの検索連動型広告も試してみましたが、ほとんど反響はありませんでした。
「前職の営業経験を生かせば何とかなるだろう」とタカをくくっていた松本氏でしたが、成果には結びつかず「自信やプライドは砕け散った」と振り返ります。
デジタルマーケティングの方向転換で下請け脱却
転機となったのは、ホームページを見た一般企業からの「社員の作業着に付けるワッペンをつくってもらえませんか」という問い合わせです。
「そんな需要があったとは」と驚いた松本氏。これぞ“鉱脈”と考え、アパレル向けだった自社サイトの文言を「刺繍入りワッペンをお作りします」と、一般企業向けに変えてみました。すると問い合わせや受注が徐々に増加します。
さらに、企業のロゴを刺繍するポロシャツを販売。効果が薄いと止めていた検索連動型広告も再開します。キーワード検索でマツブンのサイトが上位に表示されるように、サイト内の各ページに「刺繍 ポロシャツ」という用語を多用しました。たちまち受注が相次ぐようになりました。
以前は「いかにアパレルメーカーの下請けに入るか」ということばかり考えていた松本氏。自社の刺繍が、オーダーメイド品や高級品と相性がいいことに気づき、その付加価値を一般企業向けにアピールして売るという方向に事業転換します。
新商品では、刺繍入りのポロシャツだけでなくTシャツや帽子などラインアップを揃え、ウェブサイトでも取り扱いを開始。高級感のある落ち着いた雰囲気へとサイトの改修も行い、自社の職人を前面に打ち出して品質の良さを訴求したところ、狙いどおりの受注を得ることができました。
展示会で着用するユニホームや、当時「クールビズ」が流行っていたことからスーツ代わりとしても活用されたそうです。注文を受けて製作したオリジナルグッズは、自社サイトで企業名とデザインを紹介。電子部品メーカーや電力会社といった多くの企業の実用例を掲載することで、新規の顧客からの注文も得やすくなりました。
また、定額制にして金額を明示したことで、サイト経由の受注率も向上。資料請求した顧客には無料でサンプルを送り信頼を得る工夫もしました。
黒字転換を果たし、売上も年10%ペースで増加
売上は年10%のペース伸び、2009年に黒字転換を果たして松本氏は社長に就任しました。その後にスタートした「今治タオル」との共同企画は、会社の周年記念品やノベルティに使用され大ヒットしたそうです。
コロナ禍においては、イベント用の商品など一部の受注は減りましたが大きな影響はなく、前年比で115%の成長を達成。2022年3月期の売上高は3億円。2000年から6倍以上の成長です。従業員も6人から20人にまで増えました。現在はECでの売り上げが全体の90%を占め、営業活動はネットや電話がメインです。
一方で松本氏は、今後の見込み顧客を開拓するべく個人のSNSアカウントを通じて情報発信を始めるなど、将来を見据えたマーケティングにも余念がありません。
Webマーケティングでは商品やサービスをどのように売り出すかが非常に重要です。ただ、自社だけで最適解を見つけることはなかなか難しく、外部から知見を得ることも有効策の一つといえます。
デジタルマーケティングに豊富な実績を有するmode株式会社では、御社に最適な戦略を見つけ出し、業績を伸ばすサービスを提供しています。より早い実現が可能となるため、検討している方はぜひ一度ご相談ください。
【会社名】会社名:mode株式会社
URL:https://mode2009.jp/
【お問い合わせ(Eメール)】:
matsushita@race-backs.co.jp(担当者:松下)
【お問い合わせ(電話)】:
080-9866-5321(担当者:松下)
20万円の高級生ハムが数量限定で出荷!“いのちのスープ”で知られる辰巳芳子氏が手がける渾身の1本

「日本で初めて生ハム作りに成功した人」は、“いのちのスープ”で知られる98歳の料理研究家・辰巳芳子氏であることをご存知でしょうか。
イタリアで料理を学んだ辰巳氏は、ローマで出合った生ハムを鎌倉で再現したいと試行錯誤を重ね、長い年月をかけて成功させました。今回、十数年ぶりに、この「辰巳芳子の生ハム」が数量限定で復活します。
バスク地方ロヨラにある修道院の製法をもとに生ハム作りを開始
辰巳氏が生ハムを初めて目にし、口にしたのは1969年と半世紀以上前。ローマで学んだイタリア料理では、生ハムが隠し味として使用されていたそうです。辰巳氏は、「これは“イタリアの鰹節”で、生ハムがなければ再現できない本場の味がある」と実感しました。
生ハムといえば、イタリアでは「プロシュット・クルード」と呼ばれ、特に「プロシュット・ディ・パルマ(パルマハム)」が有名。ただし彼女が出合い、 再現を望んだのは、「ハモン・セラーノ」というスペインで作られる生ハムです。
これは塩漬けにした豚肉を、高燥地に長期間吊るし、乾燥させて作ります。そのため、湿度が高く夏場の気温も高い日本で作ることは難しいといわれていました。
帰国後、神奈川県鎌倉市の自宅にいた辰巳氏は山を抜けて庭を渡る風に頬をなでられ、「これなら生ハムが作れるのではないか」との天啓を得ます。そこで3〜4年間、小さな生ハム作りに挑戦するも失敗。「手作りの現場を見られるスペインへ行きたい」という思いが募って1975年、スペイン全土の生ハム作りの現場を巡りました。
最後に日本と気候が似ているバスク地方ロヨラにある修道院を訪れたところ、その製法も規模も鎌倉で再現できると感じ、帰国後に本格的な生ハムづくりを開始。専用の小屋も建築しました。
辰巳氏は、「諦めるなんてこれっぽっちも考えたことがなかったわね。楽しくて仕方なかった。掘り下げても終わりがない。その結果、いのちとは何かってことに行き着いてしまうのよ、どうしても。なぜ食べるのか。なぜ食べなければならないのかを突き詰めることになるの」と、当時の思いを振り返ります。
味は本場のスペインやイタリア以上
その後、15年にわたって改良を重ね、辰巳氏は生ハムを完成させました。極めて伝統的な製法を基本に、添加物は一切使用しませんが、鎌倉の気候に合わせて温度・湿度・塩の分量・風量を管理して作ったものです。
辰巳氏は、「味はスペインやイタリアの生ハム以上であると思っています。それは、試行錯誤を繰り返す中で、日本人でなければやらない手間をかけているから」と説明します。
「風味といい、熟成の味わいといい、(この生ハムは)豚肉料理の中で、最もおいしいと思っています。多くの業者がイタリア人を招聘してトライしたが完成できなかった。スペインから訪れた人たちも、日本人がこんな生ハムを作れるのかと、賞賛半分、畏れ半分でしたね」。
当時、求めに応じて大分県の業者に製法を伝えていましたが、のちに業者は廃業。辰巳氏も1998年頃には生ハム作りをやめていました。すると、「もう一度食べたい」「あの製法を伝承すべき」と、惜しむ声があちこちから上がります。
そこで、東京大学・早稲田大学の研究者とシェフを巻き込むプロジェクトが、2016年から開始されたのです。そこから生ハム小屋はフル稼動となり、数種の豚もも肉、100本弱が熟成を待つようになりました。
11月に仕込みを開始し、まずは1本10~15kgの豚後足から大腿骨を外して、余分な血や水分を抜きます。これにヨーロッパでは岩塩を用いますが、日本各地の自然海塩を丁寧にすりこみ、冷蔵室に吊るして乳酸菌発酵を促すのです。その他、気候に合わせた工夫を凝らしています。
塩気がマイルドでこの上なく上品な味わい
今回、限定販売となる生ハムには、高品質な「庄内豚」を使用。空気と水に恵まれた山形県鶴岡市に新設された工場で、仕込みと熟成を進めています。第一弾の出荷は、2024年春を予定しています。
このプロジェクトをサポートする1人、東京都渋谷区恵比寿にある「タイユバン・ロブション」の元料理長で「モナリザ」総料理長の河野透シェフは、「塩気がマイルドでこの上なく上品な味わい」「クセやにおいはないのに、旨み、風味がぎゅっと凝縮されている、まさに熟成の味わい。いつでもいくらでも食べられる。最高峰の生ハム」「スペインのイベリコに全く引けをとらないというか、もっとおいしいと思った」と絶賛しています。
今回は「ハモンクルード アラタツミ」として、生ハム骨付き原木の先行予約が開始されました。原木1本24か月熟成もので、税込み19万8000円、先着順で販売します。K・Pクリエイションズ株式会社、電話は03-6812-9705、E-MAILではkoyanagi@koyanagi.co.jpにて、受けつけているとのことです。
クラフトジンの製造に挑んだ合成樹脂メーカー!本業との共通点を見出しブランディングに活用
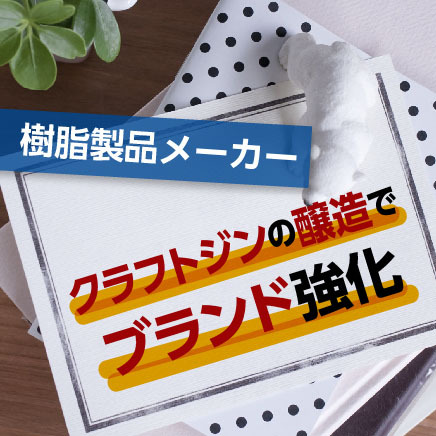
合成樹脂製品メーカー、株式会社大信が異業種での新事業として生産・販売を始めたクラフトジンの売れ行きが好調です。本業にも好影響をもたらしていることから、脚光を浴びています。
本業と無縁であった分野でビジネスを展開するに至った理由、そこで成功をおさめた秘密はどこにあるのでしょうか。先行きの見通しが芳しくない業界で生き残りを模索する企業が少なくない中、大信の取り組みはその参考となるかもしれません。
老舗メーカーの弱点は広告戦略だった
大信は1949年に創業。プラスチック材料を様々な形に成形する技術を武器とし、アルミサッシの機密材、交通インフラ系製品の部品などを生産してきた企業です。
グループ4社で従業員は約150名を数え、グループ全体での年商は約20億円です。設計から金型製作、材料開発、成形、加工。これらを一括で担えることで存在感を発揮してきました。
同社の技術をもとにした商品の一つが樹脂を用いた「内窓プラスト」です。気密性に優れ、高い断熱性・防音性などを備える内窓で、北海道を中心に使用されてきました。同社を代表する商品です。
ただ、創業者の孫である3代目、中澤眞新太郎さんは建材業界が縮小傾向にあることから、商品が飽和状態にあることを懸念していました。様々な業界を経験したのち、29歳で家業の世界に飛び込んだ中澤氏は、同社にマーケティングやブランディングの戦略が欠如していることにも気づきました。
クラフトジン製造・販売に生かされた本業のノウハウ
中澤氏はマーケティングやブランディングの重要性を社内で訴え、ときに説得しながらそれらの強化を図り、ガラス店やサッシ店がメーカーから仕入れたガラスを組み入れたセット品の販売に注力。売上を入社前から10倍に伸ばす実績をあげました。
ただ、目先の売上は伸びても、中澤氏は「国内の樹脂関連事業には伸びしろがない」と考えていました。それは自社の将来が安泰ではないことも意味しています。そのため付加価値の高い商品、あるいは海外での展開など方向性を模索していたそうです。
その中で手がけることになった新事業がクラフトジンの製造・販売でした。2021年12月、東京・八王子にある同社の工場の近くに「東京八王子蒸留所」を創設。2022年1月から、「トーキョーハチオウジン」と命名して販売をスタートしました。
月に約1000本を製造し、初回の蒸留分は2週間で完売、同年5月には「東京ウイスキー&スピリッツコンペティション2022」で金賞と銀賞を受賞しました。さらに香港・台湾・シンガポールへの輸出もスタートするなど好評を博しているそうです。
新事業が本業の知名度向上に寄与
一見して樹脂メーカーとは縁のなさそうなクラフトジンの製造を始めたきっかけは、中澤氏が出張先の北海道のバーでたしなんだジンに感動したことでした。ジンの魅力に惹かれていろいろとジンの世界を知るうちに、中澤氏は樹脂製品の製造工程とジンの蒸留工程、その流れも似ていることを発見します。
もともと飲食業界に身を置いていたこともある中澤氏は、ジンのカクテルづくりにおける汎用性や、クラフトジンが海外で人気になっていることなどから「取り扱う価値がある」と感じたそうです。
自らアメリカのメーカーに研修に出向いて設備や作り方などについて学んだうえで、ドイツの技術者のアドバイスも受けて準備を開始。その過程では大信が培ってきた工場建設のノウハウもいかされることになりました。このようにして蒸留所のオープンにこぎつけました。
クラフトジンの製造・販売は、同社の家業にもプラスに働いていると言います。商品は取引先の手みやげとして使用することがあるそうですが、持参すると驚かれるとともに、未来への取り組みをする企業というイメージアップにつながっている実感があるそうです。
またトーキョーハチオウジンは海外への輸出も始まっていますが、それが樹脂の海外展開につながる可能性も感じているそうです。クラフトジンの輸出により大信の認知度向上につながっていけば、以前から模索していた海外での事業も視野に入ってくることが考えられます。
東京八王子蒸留所の公式サイトでは、ものづくりの文化と歴史を育んできた八王子や大信工業を織り交ぜたストーリーを掲載しています。大信の高い技術とそこから生まれた商品を紹介しながらその技術力がジンの製造にも生かされていることを伝えているのです。
思いがけない出会いから「クラフトジンを作りたい」という3代目の発案と情熱からスタートした新事業は樹脂メーカーとしての本業のマーケティングやブランディングにも貢献しているようです。